上 つれづれなるまゝに
序段
つれづれなるまゝに、日ぐらし硯にむかひて、心にうつりゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ。
第一段
いでや此の世にうまれては、ねがはしかるべき事こそおほかめれ。御門の御位は、いともかしこし。竹の園生の末葉まで、人間の種ならぬぞやんごとなき。一の人の御有樣はさらなり、たゞ人も、舎人など給はるきははゆゝしと見ゆ。其の子孫までは、はふれにたれど、なほなまめかし。それよりしもつかたは、ほどにつけつゝ、時にあひ、したりがほなるも、みづからはいみじと思ふらめど、いとくちをし。
法師ばかりうらやましからぬものはあらじ、「人には木の端のやうに思はるゝよ」と清少納言がかけるも、げにさることぞかし。いきほひまうにのゝしりたるにつけて、いみじとは見えず、増賀ひじりのいひけんやうに名聞くるしく、佛の御をしへにたがふらんとぞおぼゆる。ひたぶるの世すて人は、なか/\あらまほしきかたもありなん。人は、かたち有樣のすぐれたらんこそ、あらまほしかるべけれ。物うちいひたる、ききにくからず、愛敬ありて、言葉多からぬこそ、飽かずむかはまほしけれ。めでたしと見る人の、心劣りせらるゝ本性みえんこそ口をしかるべけれ。しなかたちこそ生れつきたらめ、心はなどか、賢きより賢きにもうつさばうつらざらん。かたち心ざまよき人も、ざえなくなりぬれば、しなくだり、顏にくさげなる人にも立ちまじりて、かけずけおさるゝこそ、ほいなきわざなれ。ありたき事は、まことしき文の道、作文、和歌、管絃の道、又有職に公事の方、人の鏡ならんこそいみじかるべけれ。手などつたなからず走りがき、聲をかしくて拍子とり、いたましうするものから、下戸ならぬこそをのこはよけれ。
第二段
いにしへのひじりの御代の政をもわすれ、民の愁へ、國のそこなはるゝをもしらず、よろづにきよらをつくしていみじと思ひ、所せきさましたる人こそ、うたて、おもふところなく見ゆれ。
「衣冠より馬車にいたるまで、有るにしたがひて用ゐよ。美麗をもとむる事なかれ」とぞ、九條殿の遺誡にも侍る。順徳院の禁中の事どもかゝせ給へるにも、「おほやけの奉り物は、おろそかなるをもてよしとす」とこそ侍れ。
第三段
萬にいみじくとも、色このまざらん男は、いとさう/\しく、玉の巵の當なきこゝちぞすべき。露霜にしほたれて、所さだめずまどひありき、親のいさめ、世のそしりをつゝむに心のいとまなく、あふさきるさに思ひみだれ、さるは獨寢がちに、まどろむ夜なきこそをかしけれ。
さりとて、ひたすらたはれたる方にはあらで、女にたやすからずおもはれんこそ、あらまほしかるべきわざなれ。
第四段
後の世の事心にわすれず、佛の道うとからぬ、こゝろにくし。
第五段
不幸に愁にしづめる人の、かしらおろしなど、ふつゝかに思ひとりたるにはあらで、あるかなきかに門さしこめて、まつこともなく明し暮したる、さるかたにあらまほし。顯基中納言のいひけん、配所の月、罪なくて見ん事、さも覺えぬべし。
第六段 わが身のやんごとなからんにも、まして數ならざらんにも、子といふものなくてありなん。
前中書王、九條太政大臣、花園左大臣、みな族絶えん事を願ひ給へり。染殿大臣も、「子孫おはせぬぞよく侍る。末のおくれ給へるはわろき事なり」とぞ、世繼の翁の物語にはいへる。聖徳太子の御墓をかねてつかせ給ひける時も、「こゝをきれ。かしこをた
て。子孫あらせじと思ふなり」と侍りけるとかや。
第七段
あだし野の露きゆる時なく、鳥部山の烟立ちさらでのみ住みはつるならひならば、いかに物のあはれもなからん。世はさだめなきこそいみじけれ。命ある物を見るに、人ばかり久しきはなし。かげろふのゆふべをまち、夏の蝉の春秋を知らぬもあるぞかし。
つく/\と一年をくらすほどだにも、こよなうのどけしや。あかずをしと思はば、千年を過ぐすとも、一夜の夢の心ちこそせめ。住み果てぬ世に、みにくき姿を待ちえて何かはせん。命ながければ辱おほし。ながくとも、四十にたらぬほどにて死なんこそ、めやすかるべけれ。
そのほど過ぎぬれば、かたちをはづる心もなく、人にいでまじらはん事を思ひ、夕の陽に子孫を愛してさかゆく末を見んまでの命をあらまし、ひたすら世をむさぼる心のみふかく、もののあはれも知らずなりゆくなんあさましき。
第八段
世の人の心まどはす事、色欲にはしかず。人の心はおろかなるものかな。にほひなどはかりのものなるに、しばらく衣裳に薫物すとしりながら、えならぬにほひには、必ずこゝろときめきするものなり。九米の仙人の、物あらふ女のはぎの白きを見て、通を失ひけんは、誠に手足肌などのきよらに肥えあぶらづきたらんは、外の色ならねば、さもあらんかし。
第九段
女は髪のめでたからんこそ、人のめたつべかめれ。人のほど、心ばへなどは、ものいひたるけはひにこそ、ものごしにも知らるれ。
事にふれて、うちあるさまにも人の心をまどはし、すべて女の、うちとけたるいも寢ず、身ををしとも思ひたらず、たふべくもあらぬ業にもよく耐へ忍ぶは、たゞ色を思ふが故なり。
まことに愛著の道、その根ふかく源とほし。六塵の樂欲おほしといへども、皆厭離しつべし。其の中に、たゞかのまどひのひとつやめがたきのみぞ、老いたるもわかきも、智あるも愚なるも、かはる所なしとみゆる。されば、女の髪すぢをよれる綱には、大象もよくつながれ、女のはける足駄にて作
れる笛には、秋の鹿必ず寄るとぞ言ひ傳へ侍る。みづから戒めて、恐るべく愼むべきは此のまどひなり。
第十段
家居のつき/\しく、あらまほしきこそ、かりのやどりとは思へど、興有るものなれ。よき人ののどやかに住みなしたる所は、さし入りたる月の色も、一きはしみ/\と見ゆるぞかし。いまめかしくきらゝかならねど、木だち物ふりて、わざとならぬ庭の草も心あるさまに、簀子、透垣のたよりをかしく、うちある調度も昔覺えてやすらかなるこそ、心にくしと見ゆれ。
おほくの工の心をつくしてみがきたて、唐の、大和の、めづらしく、えならぬ調度どもならべおき、前栽の草木まで心のまゝならず作りなせるは、見る目も苦しく、いとわびし。さてもやはながらへ住むべき。又時のまの烟ともなりなんとぞ、うち見るよりおもはるゝ。大方は家居にこそ、ことざまはおしはからるれ。後徳大寺大臣の寢殿に、鳶ゐさせじとて繩をはられたりけるを、西行が見て、「鳶のゐたらんは、何かはくるしかるべき。此の殿の御心、さばかりにこそ」とて、そののちはまゐらざりけると聞き侍るに、綾小路宮のおはします小坂どのの棟に、いつぞや繩をひかれたりしかば、かのためし思ひいでられ侍りしに、誠や、「烏のむれゐて、池の蛙をとりければ、御覧じ悲しませ給ひてなん」と、人の語りしこそ、さてはいみじくこそと覺えしか。徳大寺にもいかなる故か侍りけん。
第十一段
神無月の比、栗栖野といふ所を過ぎて、ある山里にたづね入る事侍りしに、遙なる苔のほそ道をふみわけて、心ぼそくすみなしたる庵あり。木の葉にうづもるゝかけ樋の雫ならでは、つゆおとなふ物なし。閼伽棚に菊紅葉など折りちらしたる、さすがにすむ人のあればなるべし。
かくてもあられけるよと、あはれに見るほどに、かなたの庭に、おほきなる柑子の木の、枝もたわゝになりたるが、まはりをきびしくかこひたりしこそ、すこしことさめて、此の木なからましかばとおぼえしか。
第十二段
おなじ心ならん人と、しめやかに物語して、をかしきことも、世のはかなき事も、うらなく言ひ慰まんこそ嬉しかるべきに、さる人有るまじければ、つゆたがはざらんとむかひ居たらんは、ひとりある心地やせん。
互に言はんほどの事をば、げにと聞くかひあるものから、いさゝか違ふ所もあらん人こそ、「我はさやは思ふ」など爭ひ憎み、「さるからさぞ」ともうち語らはば、つれづれなぐさまめとおもへど、げには少しかこつ方も、我とひとしからざらん人は、大方のよしなしごと言はんほどこそあらめ、まめやかの心の友には、はるかにへだたる所の有りぬべきぞわびしきや。
第十三段
ひとり燈のもとに文をひろげて、見ぬ世の人を友とするぞ、こよなう慰むわざなる。文は、文選のあはれなる巻々、白氏文集、老子のことば、南華の篇。此の國の博士どものかけるものも、いにしへのは、あはれなる事多かり。
第十四段
和歌こそなほをかしきものなれ。あやしのしづ山がつのしわざも、いひ出づればおもしろく、おそろしき猪のしゝも、「ふす猪の床」といへばやさしくなりぬ。
この比の歌は、一ふしをかしくいひかなへたりと見ゆるはあれど、ふるき歌どものやうに、いかにぞや、ことばの外にあはれにけしきおぼゆるはなし。貫之が、「いとによる物ならなくに」といへるは、古今集の中の歌くづとかやいひつたへたれど、今の世の人のよみぬべきことがらとはみえず。其の世の歌には、すがた、言葉、此のたぐひのみ多し。此の歌に限りてかくいひたてられたるも、しりがたし。源氏物語には、「ものとはなしに」とぞかける。新古今には、「のこる松さへ峰にさびしき」といへる歌をぞ言ふなるは、まことに、少しくだけたるすがたにもや見ゆらん。されどこの歌も、衆議判の時、よろしきよし沙汰ありて、後にも殊更に感じ仰せ下されけるよし、家長が日記にはかけり。
歌の道のみ古に變らぬなどいふ事もあれど、いさや。今もよみあへるおなじ詞、歌枕も、昔の人のよめるは、さらに同じものにあらず。やすくすなほにして、姿もきよげに、あはれもふかくみゆ。梁塵秘抄の郢曲の言葉こそ、又あはれなることはおほかめれ。昔の人は、たゞいかに言ひ捨てたることぐさも、皆いみじくきこゆるにや。
第十五段
いづくにもあれ、しばし旅だちたるこそ、めさむる心地すれ。そのわたり、こゝかしこ見ありき、ゐなかびたる所、山里などは、いとめなれぬ事のみぞ多かる。都へ便求めて文やる、「その事かの事、便宜にわするな」など言ひやるこそをかしけれ。
さやうの所にてこそ、よろづに心づかひせらるれ。もてる調度まで、よきはよく、能ある人、かたちよき人も、常よりはをかしとこそ見ゆれ。寺、社などに、しのびてこもりたるもをかし。
第十六段
神樂こそ、なまめかしく、おもしろけれ。おほかたもののねには笛、篳篥。常に聞きたきは、琵琶、和琴。
第十七段
山寺にかきこもりて佛につかうまつるこそ、つれ/\もなく、心の濁も清まる心地すれ。
第十八段
人は己をつゞまやかにし、おごりを退けて財をもたず、世をむさぼらざらんぞいみじかるべき。むかしより、賢き人の富めるは稀なり。
唐土に許由といひつる人は、さらに身にしたがへる貯もなくて、水をも手してさゝげて飲みけるを見て、なりひさごといふ物を人のえさせたりければ、或時、木の枝に掛けたりけるが、風にふかれて鳴りけるを、かしがましとて捨てつ。また手にむすびてぞ水ものみける。いかばかり心のうち涼しかりけん。孫晨は冬の月に衾なくて、藁一束ありけるを、夕には是にふし、朝にはをさめけり。もろこしの人は、これをいみじとおもへばこそ、しるしとゞめて世にも傳へけめ、これらの人は、語りも傳ふべからず。
第十九段
折節の移りかはるこそ、ものごとにあはれなれ。「もののあはれは秋こそまされ」と、人ごとに言ふめれど、それもさるものにて、今一きは心もうきたつものは、春の氣色にこそあめれ。鳥の聲などもことの外に春めきて、のどやかなる日影に牆根の草萌え出づる頃より、やゝ春ふかく霞みわたりて、花もやう/\けしきだつほどこそあれ、をりしも雨風うち續きて、こゝろあわたゞしく散り過ぎぬ。青葉になり行くまで、よろづにたゞ心をのみぞ惱ます。花橘は名にこそ負へれ、なほ梅のにほひにぞ、古の事も立ちかへり、戀しう思ひいでらるゝ。山吹のきよげに、藤のおぼつかなきさましたる、すべて思ひすてがたき事多し。「灌佛の比、祭の比、若葉の梢涼しげに茂りゆくほどこそ、世のあはれも、人の戀しさもまされ」と人のおほせられしこそ、げにさるものなれ。五月、あやめふく比、早苗とる比、水鶏のたゝくなど、心ぼそからぬかは。六月の比、あやしき家にゆふがほの白く見えて、蚊遣火ふすぶるもあはれなり。六月祓またをかし。七夕まつるこそなまめかしけれ。やう/\夜寒になるほど、雁なきて來る比、萩の下葉色づくほど、わさ田刈り干すなど、とりあつめたる事は秋のみぞ多かる。又野分の朝こそをかしけれ。いひつゞくれば、みな源氏物語、枕草子などにことふりにたれど、同じ事、また今さらにいはじとにもあらず。おぼしき事いはぬは腹ふくるゝわざなれば、筆にまかせつゝ、あぢきなきすさびにて、かつやりすつべき物なれば、人の見るべきにもあらず。
さて、冬枯のけしきこそ、秋にはをさ/\劣るまじけれ。汀の草に紅葉の散りとゞまりて、霜いと白うおける朝、遣水より烟のたつこそをかしけれ。年の暮れはてて、人ごとに急ぎあへる比ぞ、又なくあはれなる。すさまじきものにして見る人もなき月の、寒けく澄める廿日あまりの空こそ、心ぼそきものなれ。御佛名、荷前の使たつなどぞ、あはれにやんごとなき。公事ども繁く、春のいそぎにとり重ねて、もよほし行はるゝさまぞいみじきや。追儺より四方拜につゞくこそ面白けれ。つごもりの夜、いたう暗きに、松どもともして、夜半すぐるまで人の門たゝき走りありきて、何事にかあらん、こと/\しくのゝしりて、足をそらにまどふが、曉がたより、さすがに音なくなりぬるこそ、年の名殘も心細けれ。なき人のくる夜とて、魂まつるわざは、此の比都にはなきを、あづまのかたにはなほする事にてありしこそ、あはれなりしか。かくて明けゆく空の氣色、昨日にかはりたりとは見えねど、ひきかへ珍しき心地ぞする。大路のさま、まつ立てわたして、花やかにうれしげなるこそ、またあはれなれ。
第二十段
なにがしとかやいひし世すて人の、「此の世のほだしもたらぬ身に、たゞ空の名殘のみぞをしき」といひしこそ、誠にさも覺えぬべけれ。
第二十一段
萬のことは、月見るにこそなぐさむものなれ。或人の、「月ばかり面白きものはあらじ」といひしに、又ひとり、「露こそあはれなれ」と爭ひしこそをかしけれ。折にふれば、何かはあはれならざらん。
月花はさらなり、風のみこそ人に心はつくめれ。岩にくだけて清く流るゝ水のけしきこそ、時をもわかずめでたけれ。「げん湘日夜東に流れさる、愁人の爲にとゞまること少時もせず」といへる詩を見侍りしこそあはれなりしか。けい康も、「山澤にあそびて魚鳥を見れば心たのしぶ」といへり。人とほく、水草清き所にさまよひありきたるばかり、心なぐさむ事はあらじ。
第二十二段
なに事も、ふるき世のみぞしたはしき。今やうは無下にいやしくこそなりゆくめれ。かの木の道の匠の造れる美しきうつは物も、古代の姿こそをかしと見ゆれ。文の詞などぞ、昔の反古どもはいみじき。たゞ言ふ言葉も、口をしうこそなりもてゆくなれ。いにしへは、「車もたげよ」、「火かゝげよ」とこそ言ひしを、今樣の人は、「もてあげよ」、「かきあげよ」といふ。「主殿寮人數たて」といふべきを、「たちあかししろくせよ」といひ、最勝講の御聽聞所なるをば、「御かうのろ」とこそいふを、「かうろ」といふ、くちをしとぞ、ふるき人はおほせられし。
第二十三段
衰へたる末の世とはいへど、なほ九重の神さびたる有樣こそ、世づかずめでたきものなれ。露臺、朝餉、何殿、何門などは、いみじともきこゆべし。あやしの所にもありぬべき小蔀、小板敷、高遣戸なども、めでたくこそきこゆれ。「陣に夜の設せよ」といふこそいみじけれ。夜御殿のをば、「かいともしとうよ」などいふ、又めでたし。上卿の、陣にて事おこなへるさまは更なり、諸司の下人どもの、したりがほになれたるもをかし。さばかり寒き夜もすがら、こゝかしこに睡り居たるこそをかしけれ。「内侍所の御鈴のおとは、めでたく優なるものなり」とぞ、徳大寺太政大臣はおほせられける。
第二十四段
齋王の野宮におはしますありさまこそ、やさしく面白き事のかぎりとは覺えしか。「經」「佛」などいみて、「なかご」「染紙」などいふなるもをかし。すべて神の社こそ、すてがたくなまめかしきものなれや。物ふりたる森のけしきもたゞならぬに、玉垣しわたして、さか木にゆふかけたるなど、いみじからぬかは。ことにをかしきは、伊勢、賀茂、春日、平野、住吉、三輪、貴布禰、吉田、大原野、松
尾、梅宮。
第二十五段
飛鳥川の淵瀬常ならぬ世にしあれば、時うつり事さり、たのしびかなしびゆきかひて、花やかなりしあたりも人住まぬのらとなり、變らぬ住家は人あらたまりぬ。桃李もの言はねば、誰と共にか昔を語らん。まして、見ぬ古のやん事なかりけん跡のみぞ、いとはかなき。京極殿、法成寺など見るこそ、志とゞまり、事變じにけるさまはあはれなれ。御堂殿の作りみがかせ給ひて、庄園おほくよせられ、我が御族のみ、御門の御うしろみ、世のかためにて、行末までとおぼしおきし時、いかならん世にも、かばかりあせはてんとはおぼしてんや。大門、金堂などちかくまで有りしかど、正和の比南門は燒けぬ。金堂は、そののちたおれふしたるまゝにて、とりたつるわざもなし。無量壽院ばかりぞ、其のかたとて殘りたる。丈六の佛九體、いとたふとくて竝びおはします。行成大納言の額、兼行がかける扉、あざやかに見ゆるぞあはれなる。法華堂などもいまだ侍るめり。是も又いつまでかあらん。かばかりの名殘だになき所々は、おのづから礎ばかり殘るもあれど、さだかに知れる人もなし。されば、萬に見ざらん世までを思ひ掟てんこそ、はかなかるべけれ。
第二十六段
風も吹きあへずうつろふ人の心の花になれにし年月を思へば、あはれと聞きしことの葉ごとに忘れぬものから、我が世の外になりゆくならひこそ、亡き人の別れよりもまさりて悲しきものなれ。
されば、白き絲の染まん事をかなしび、路のちまたのわかれん事を嘆く人も有りけんかし。堀川院の百首の歌の中に、昔見し妹が墻根は荒れにけりつばなまじりの菫のみしてさびしきけしき、さる事侍りけん。
第二十七段
御國ゆづりの節會行はれて、劍、璽、内侍所わたし奉らるゝほどこそ、限なう心細けれ。新院のおりさせ給ひての春、よませ給ひけるとかや、殿もりのとものみやつこよそにしてはらはぬ庭に花ぞちりしく今の世のこと繁きにまぎれて、院には參る人もなきぞさびしげなる。かゝる折にぞ、人の心もあらはれぬべき。
第二十八段
諒闇の年ばかりあはれなる事はあらじ。倚廬の御所のさまなど、板敷をさげ、あしの御簾をかけて、布のもかうあら/\しく、御調度どもおろそかに、皆人のさうぞく、太刀、平緒まで異樣なるぞゆゝしき。
第二十九段
しづかに思へば、よろづに過ぎにしかたの戀しさのみぞせんかたなき。人しづまりて後、ながき夜のすさびに、なにとなき具足とりしたゝめ、殘しおかじと思ふ反古などやりすつる中に、亡き人の、手ならひ、繪かきすさびたる見出でたるこそ、たゞその折の心地すれ。此の比ある人の文だに、久しくなりて、いかなるをり、いつの年なりけんと思ふは、あはれなるぞかし。手なれし具足なども、心もなくてかはらず久しき、いとかなし。
第三十段
人のなきあとばかり悲しきはなし。中陰のほど、山里などにうつろひて、便あしくせばき所にあまたあひゐて、後のわざども營みあへる、心あわたゞし。日數のはやく過ぐるほどぞ、ものにも似ぬ。はての日は、いと情なう、たがひに言ふ事もなく、我かしこげに物ひきしたゝめ、ちりぢりに行きあかれぬ。もとのすみかに歸りてぞ、更に悲しき事は多かるべき。「しかじかのことは、あなかしこ、跡のためいむなる事ぞ」などいへるこそ、かばかりのなかに何かはと、人の心はなほうたておぼゆれ。年月へても、つゆ忘るゝにはあらねど、去る者は日々に疎しといへることなれば、さはいへど、其のきはばかりは覺えぬにや、よしなしごと言ひてうちも笑ひぬ。からはけうとき山の中にをさめて、さるべき日ばかりまうでつゝ見れば、ほどなく卒都姿も苔むし、木の葉ふりうづみて、夕の嵐、夜の月のみぞ、こととふよすがなりける。
思ひ出でてしのぶ人あらんほどこそあらめ、そも又ほどなく失せて、聞きつたふるばかりの末々は、あはれとやは思ふ。さるは、跡とふわざも絶えぬれば、いづれの人と名をだに知らず、年々の春の草のみぞ、心あらん人はあはれと見るべきを、はては、嵐にむせびし松も千年をまたで薪にくだかれ、古き墳はすかれて田となりぬ。そのかただになくなりぬるぞ悲しき。
第三十一段
雪のおもしろうふりたりし朝、人のがりいふべき事ありて文をやるとて、雪のことなにとも言はざりし返事に、「此の雪いかゞ見ると、一筆のたまはせぬほどのひが/\しからん人の仰せらるゝ事、きゝいるべきかは。返す/\口をしき御心なり」といひたりしこそ、をかしかりしか。いまはなき人なれば、かばかりの事もわすれがたし。
第三十二段
九月廿日の比、ある人にさそはれ奉りて、明くるまで月見ありく事侍りしに、おぼしいづる所ありて、案内せさせて入り給ひぬ。荒れたる庭の露しげきに、わざとならぬにほひしめやかにうちかをりて、しのびたるけはひ、いとものあはれなり。よきほどにて出で給ひぬれど、なほ事ざまの優におぼえて、物のかくれよりしばし見ゐたるに、妻戸を今すこしおしあけて、月見るけしきなり。やがてかけこもらましかば、くちをしからまし。跡まで見る人ありとはいかでか知らん。かやうの事は、ただ朝夕の心づかひによるべし。その人ほどなく失せにけりと聞き侍りし。
第三十三段
今の内裏作り出されて、有職の人々に見せられけるに、いづくも難なしとて、すでに遷幸の日近くなりけるに、玄輝門院御覧じて、「閑院殿のくしがたの穴は、まろく、ふちもなくてぞありし」と仰せられける、いみじかりけり。是はえふの入りて、木にてふちをしたりければ、あやまりにて、なほされにけり。
第三十四段
甲香は、ほら貝のやうなるが、ちひさくて、口のほどのほそながにしていでたる貝のふたなり。武藏の國金澤といふ浦にありしを、所の者は、「へなたりと申し侍る」とぞいひし。
第三十五段
手のわろき人の、はゞからず文書きちらすはよし。見苦しとて人にかゝするはうるさし。
第三十六段
久しくおとづれぬ比、いかばかり恨むらんと、我がおこたり思ひ知られて、言葉なき心地するに、女のかたより、「仕丁やある、ひとり」などいひおこせたるこそ、有りがたく嬉しけれ。「さる心ざましたる人ぞよき」と、人の申し侍りし、さもあるべき事なり。
第三十七段
朝夕へだてなく馴れたる人の、ともある時、我に心おき、ひきつくろへるさまに見ゆるこそ、今更かくやはなどいふ人も有りぬべけれど、なほげに/\しくよき人かなとぞおぼゆる。うとき人の、うちとけたる事などいひたる、又よしとおもひつきぬべし。
第三十八段
名利につかはれて、しづかなるいとまなく、一生を苦しむるこそおろかなれ。財多ければ、身を守るにまどし。害をかひ、累をまねくなかだちなり。身の後には金をして北斗をさゝふとも、人のためにぞわづらはるべき。おろかなる人の目をよろこばしむるたのしみ、またあぢきなし。大きなる車、肥えたる馬、金玉のかざりも、こゝろあらん人は、うたておろかなりとぞ見るべき。金は山にすて、玉は淵に投ぐべし。利にまどふは、すぐれておろかなる人なり。埋れぬ名を永き世に殘さんこそ、あらまほしかるべけれ。位高くやん事なきをしも、すぐれたる人とやはいふべき。おろかにつたなき人も、家に生れ時にあへば、高き位にのぼり、おごりをきはむるもあり。いみじかりし賢人聖人、みづから卑しき位にをり、時にあはずしてやみぬる、又おほし。ひとへに高きつかさ位をのぞむも、次におろかなり。智慧と心とこそ、世にすぐれたる譽も殘さまほしきを、つら/\思へば、譽を愛するは、人の聞きを喜ぶなり。ほむる人、そしる人、共に世にとゞまらず。傳へ聞かん人、又々すみやかに去るべし。誰をか恥ぢ、誰にか知られん事を願はん。譽は又毀の本なり。身の後の名殘りてさらに益なし。是を願ふも、次におろかなり。たゞし、しひて智を求め賢を願ふ人のためにいはば、智慧出でては僞あり。才能は煩惱の増長せるなり。傳へて聞き、學びて知るは誠の智にあらず。いかなるをか智といふべき。可不可は一條なり。いかなるをか善といふ。まことの人は、智もなく、徳もなく、功もなく、名もなし。誰か知り誰か傳へん。是れ徳をかくし愚をまもるにはあらず。もとより賢愚得失のさかひにをらざればなり。まよひの心をもちて名利の要をもとむるに、かくのごとし。萬事は皆非なり。いふにたらず、願ふにたらず。
第三十九段 或人、法然上人に、「念佛の時、睡におかされて行をおこたり侍る事、いかゞして此のさはりをやめ侍らん」と申しければ、「目のさめたらんほど念佛し給へ」とこたへられたりける、いとたふとかりけり。又、「往生は、一定と思へば一定、不定と思へば不定なり」といはれけり。これもたふとし。又、「うたがひながらも念佛すれば往生す」ともいはれけり。これも又たふとし。
第四十段 因幡國に何の入道とかやいふ者の娘、かたちよしときゝて、人あまたいひわたりけれども、此の娘、たゞ栗をのみ食ひて、更によねのたぐひをくはざりければ、「かゝることやうのもの、人にみゆべきにあらず」とて、親許さざりけり。
第四十一段
五月五日、賀茂のくらべ馬を見侍りしに、車の前に雜人立ちへだてて見えざりしかば、各おりて埒の際に寄りたれど、殊に人多く立ちこみて、分け入りぬべきやうもなし。かゝる折に、むかひなるあふちの木に、法師の登りて、木のまたについゐて物見るあり。とりつきながら、いたう睡りて、落ちぬべき時に目をさます事度々なり。これを見る人、あざけりあざみて、「世のしれものかな。かく危き枝の上にて、やすき心ありて睡るらんよ」といふに、我が心にふと思ひしまゝに、「我等が生死の到來、只今にもやあらん。それを忘れて、物見て日を暮らす、愚なる事は、なほまさりたるもの
を」といひたれば、前なる人ども、「誠にさにこそ候ひけれ。尤もおろかに候」といひて、皆後を見返りて、「こゝへ入らせ給へ」とて、所をさりてよび入れ侍りにき。かほどのことわり、誰かは思ひよらざらんなれども、折からの思ひかけぬ心地して、胸に當りけるにや。人木石にあらねば、時にとりて物に感ずる事なきにあらず。
第四十二段
唐橋中將といふ人の子に、行雅僧都とて、教相の人の師する僧有りけり。氣の上る病ありて、年のやう/\たくるほどに、鼻の中ふたがりて、息も出でがたかりければ、さま/\につくろひけれど、わづらはしくなりて、目、眉、額などもはれまどひて、うちおほひければ、物も見えず、二の舞の面のやうにみえけるが、たゞおそろしく、鬼のかほになりて、目は頂の方につき、額のほど鼻になりなどして、後は坊のうちの人にも見えずこもりゐて、年久しくありて、なほわづらはしくなりて死ににけり。
かゝる病も有る事にこそありけれ。
第四十三段
春の暮つかた、のどやかに艶なる空に、いやしからぬ家の、奥深く、木だち物ふりて、庭に散りしをれたる花、見過ぐしがたきを、さし入りて見れば、南面の格子皆おろして淋しげなるに、東にむきて妻戸のよきほどにあきたる、御簾のやぶれより見れば、かたちきよげなる男の、とし廿ばかりにて、うちとけたれど、心にくゝのどやかなるさまして、机の上に文をくりひろげて見ゐたり。いかなる人なりけん、たづねきかまほし。
第四十四段
あやしの竹のあみ戸のうちより、いと若き男の、月影に色あひさだかならねど、つやゝかなる狩衣に、濃き指貫、いと故づきたるさまにて、さゝやかなる童ひとりを具して、遙なる田の中の細道を、稻葉の露にそぼちつゝ分け行くほど、笛をえならず吹きすさびたる、あはれと聞き知るべき人もあらじと思ふに、ゆかん方知らまほしくて、見送りつゝ行けば、笛を吹きやみて、山のきはに惣門のあるうちに入りぬ。榻にたてたる車の見ゆるも、都よりは目とまる心地して、下人に問へば、「しか/\の宮のおはします比にて、御佛事などさふらふにや」といふ。御堂の方に法師ども參りたり。夜寒の風にさそはれ來るそらだき物のにほひも、身にしむ心地す。寢殿より御堂の廊に通ふ女房の追風用意など、人目なき山里ともいはず心遣ひしたり。心のまゝに茂れる秋ののらは、置き餘る露にうづもれて、蟲の音かごとがましく、遣水の音のどやかなり。都の空よりは雲の往來もはやき心地して、月の晴れ曇る事定めがたし。
第四十五段
公世の二位のせうとに、良覺僧正と聞えしは、極めて腹あしき人なりけり。坊の傍に大きなる榎の木の有りければ、人「榎の木の僧正」とぞいひける。この名然るべからずとて、かの木をきられにけり。其の根のありければ、「きりくひの僧正」といひけり。いよ/\腹立ちて、きりくひをほり捨てたりければ、その跡大きなる堀にてありければ、「堀池の僧正」とぞいひける。
第四十六段
柳原の邊に、強盗法印と號する僧ありけり。たび/\強盗にあひたるゆゑに、この名をつけにけるとぞ。
第四十七段
或人清水へ參りけるに、老いたる尼の行きつれたりけるが、道すがら「くさめ/\」といひもてゆきければ、「尼御前、何事をかくはのたまふぞ」と問ひけれども、いらへもせず、なほいひやまざりけるを、度々とはれて、うち腹立ちて、「やゝ、はなひたる時、かくまじなはねば死ぬるなりと申せば、養ひ君の比叡山に兒にておはしますが、たゞ今もやはなひ給はんと思へば、かく申すぞかし」といひけり。有り難き志なりけんかし。
第四十八段
光親卿、院の最勝講奉行してさぶらひけるを、御前へ召されて、供御をいだされて食はせられけり。さて、食ひ散らしたる衝重を、御簾の中へさし入れて、罷り出でにけり。女房、「あなきたな、誰にとれとてか」など申しあはれければ、「有職の振舞、やんごとなき事なり」と、返す/\感ぜさせ給ひけるとぞ。
第四十九段
老來りて始めて道を行ぜんと待つことなかれ。ふるき墳、多くは是れ少年の人なり。はからざるに病をうけて、忽にこの世を去らんとする時にこそ、はじめて過ぎぬるかたのあやまれる事は知らるなれ。あやまりといふは、他の事にあらず、速にすべき事をゆるくし、ゆるくすべきことをいそぎて過ぎにし事のくやしきなり。其の時悔ゆともかひあらんや。人はたゞ無常の身にせまりぬる事を、心にひしとかけて、つかのまも忘るまじきなり。さらば、などか此の世の濁も薄く、佛道を勤むる心もまめやかならざらん。昔ありける聖は、人來りて自他の要事をいふ時、答へて云はく、「今、火急の事ありて、既に朝夕にせまれり」とて、耳をふたぎて念佛して、遂に往生を遂げけりと、禪林の十因に侍り。心戒といひける聖は、あまりに此の世のかりそめなる事を思ひて、靜かについゐけることだになく、常はうづくまりてのみぞありける。
第五十段
應長の比、伊勢の國より、女の鬼になりたるをゐてのぼりたりといふ事ありて、その比廿日ばかり、日ごとに、京白川の人、鬼見にとて出でまどふ。「昨日は西園寺に參りたりし、今日は院へ參るべし。たゞ今はそこ/\に」などいひあへり。まさしく見たりといふ人もなく、そらごとと云う人もなし。上下たゞ鬼の事のみいひやまず。其の比、東山より安居院邊へ罷り侍りしに、四條よりかみざまの人、皆北をさして走る。「一條室町に鬼あり」とのゝしりあへり。今出川の邊より見やれば、院の御棧敷のあたり、更に通り得べうもあらず立ちこみたり。はやく跡なき事にはあらざめりとて、人をやりて見するに、おほかたあへる者なし。暮るゝまでかく立騒ぎて、はては鬪諍おこりて、あさましきことどもありけり。その比、おしなべて二三日人のわづらふ事侍りしをぞ、かの鬼のそらごとは、此のしるしをしめすなりけりといふ人も侍りし。
第五十一段
龜山殿の御池に大井川の水をまかせられんとて、大井の土民におほせて、水車をつくらせられけり。多くの錢を給ひて、數日にいとなみいだしてかけたりけるに、大方めぐらざりければ、とかくなほしけれども、終にまはらで、徒らにたてりけり。さて、宇治の里人を召してこしらへさせられければ、やすらかにゆひて參らせたりけるが、思ふやうにめぐりて、水をくみ入るゝ事めでたかりけり。
萬に其の道を知れる者は、やんごとなきものなり。
第五十二段
仁和寺にある法師、年よるまで石清水ををがまざりければ、心うく覺えて、或時思ひ立ちて、たゞ一人かちより詣でけり。極樂寺、高良などををがみて、かばかりと心得て歸りにけり。さてかたへの人にあひて、「年比思ひつること果たし侍りぬ。聞きしにも過ぎて尊くこそおはしけれ。そも、參りたる人ごとに山へ登りしは、何事かありけん、ゆかしかりしかど、神へ參るこそ本意なれと思ひて、山までは見ず」とぞいひける。少しのことにも、先達はあらまほしき事なり。
第五十三段
是も仁和寺の法師、童の法師にならんとする名殘とて、各あそぶ事ありけるに、醉ひて興にいるあまり、傍なる足鼎をとりて頭にかづきたれば、つまるやうにするを、鼻をおしひらめて顏をさし入れて舞ひ出でたるに、滿座興に入る事かぎりなし。しばしかなでて後ぬかんとするに、大方ぬかれず。酒宴ことさめて、いかゞはせんとまどひけり。とかくすれば、くびのまはりかけて、血たり、たゞはれにはれみちて、息もつまりければ、打ち割らんとすれど、たやすく割れず、響きて堪へがたかりければ、かなはで、すべきやうなくて、三足なる角の上に帷子をうち掛けて、手をひき、杖を
つかせて、京なる醫師のがり率て行きける、道すがら人の怪しみ見る事限なし。醫師のもとにさし入りて、むかひゐたりけん有樣、さこそ異樣なりけめ。物をいふも、くゞもり聲にひゞきて聞えず。「かゝることは文にも見えず、傳へたる教もなし」といへば、又仁和寺へ歸りて、親しき者、老いたる母など、枕上に寄りゐて泣き悲しめども、
聞くらんとも覺えず。
かゝるほどに、或者のいふやう、「たとひ耳鼻こそ切れ失すとも、命ばかりはなどか生きざらん。たゞ力をたててひきにひき給へ」とて、藁のしべをまはりにさし入れて、かねを隔てて、頸もちぎるばかり引きたるに、耳鼻かけうげながらぬけにけり。から
き命まうけて、久しく病みゐたりけり。
第五十四段
御室に、いみじき兒のありけるを、いかでさそひ出して遊ばんとたくむ法師ども有りて、能あるあそび法師どもなどかたらひて、風流の破子やうのもの、ねんごろにいとなみいでて、箱風情の物にしたゝめ入れて、雙の岡の便よき所に埋みおきて、紅葉散らしかけなど、思ひよらぬさまにして、御所へ參りて、兒をそゝのかし出でにけり。うれしと思ひて、こゝかしこ遊びめぐりて、ありつる苔のむしろに竝みゐて、「いたうこそ困じにたれ。あはれ紅葉をたかん人もがな。驗あらん僧達祈り試みられよ」などいひしろひて、埋みつる木のもとにむきて數珠おしすり、印こと/\しく結び出でな
どして、いらなくふるまひて、木の葉をかきのけたれど、つや/\物も見えず。所の違ひたるにやとて、掘らぬ處もなく山をあされども、なかりけり。埋みけるを人の見おきて、御所へ參りたる間に、盗めるなりけり。法師ども言の葉なくて、聞きにくくいさかひ、腹立ちて歸りにけり。あまりに興あらんとする事は、必ずあいなきものなり。
第五十五段
家の作りやうは、夏をむねとすべし。冬はいかなる所にも住まる。暑き比、わろき住居は堪へがたき事なり。深き水は涼しげなし。淺くて流れたる、遙に涼し。こまかなる物を見るに、遣戸は蔀のまよりもあかし。天井の高きは、冬寒く、燈暗し。造作は、用なき所を作りたる、見るも面白く、萬の用にも立ちてよしとぞ、人の定めあひ侍りし。
第五十六段
久しくへだたりて逢ひたる人の、我が方にありつる事、數々に殘なく語りつゞくるこそあいなけれ。へだてなく馴れぬる人も、程經て見るは、はづかしからぬかは。つぎざまの人は、あからさまに立ち出でても、けふありつる事とて、息もつぎあへず語り興ずるぞかし。よき人の物語するは、人あまたあれど、一人に向きていふを、おのづから人も聞くにこそあれ。よからぬ人は、誰ともなく、あまたの中にうち出でて、見ることのやうに語りなせば、皆同じく笑ひのゝしる、いとらうがはし。をかしき事をいひてもいたく興ぜぬと、興なき事をいひてもよく笑ふにぞ、品のほどはかられぬべき。
人のみざまのよしあし、ざえある人は其の事など定めあへるに、己が身をひきかけていひ出でたる、いとわびし。
第五十七段
人のかたり出でたる歌物語の、歌のわろきこそほいなけれ。少し其の道知らん人は、いみじと思ひては語らじ。すべていとも知らぬ道の物語したる、かたはらいたく、聞きにくし。
第五十八段
「道心あらば、住む所にしもよらじ。家にあり、人にまじはるとも、後世をねがはんに難かるべきかは」といふは、さらに後世知らぬ人なり。げには、此の世をはかなみ、必ず生死を出でんと思はんに、なにの興ありてか、朝夕君に仕へ、家をかへりみるいとなみのいさましからん。心は縁にひかれてうつるものなれば、閑かならでは道は行じがたし。
そのうつはもの昔の人に及ばず、山林に入りても、餓をたすけ嵐を防ぐよすがなくてはあられぬわざなれば、おのづから世をむさぼるに似たる事も、たよりにふれば、などかなからん。さればとて、「そむけるかひなし。さばかりならば、なじかは捨てし」などいはんは、無下の事なり。さすがに一度道に入りて世をいとはん人、たとひ望ありとも、勢ある人の貪欲多きに似るべからず。紙の衾、麻の衣、一鉢のまうけ、あかざのあつ物、いくばくか人の費をなさん。求むる所はやすく、其の心はやく足りぬべし。かたちにはづる所もあれば、さはいへど、惡には疎く、善には近づく事のみぞ多き。人と生れたらんしるしには、いかにもして世をのがれんことこそあらまほしけれ。ひとへにむさぼる事をつとめて、菩提におもむかざらんは、萬の畜類にかはる所あるまじくや。
第五十九段
大事を思ひたゝん人は、去りがたく、心にかゝらん事の本意を遂げずして、さながら捨つべきなり。「しばし此の事はてて」、「おなじくはかの事沙汰しおきて」、「しかじかの事、人の嘲やあらん、行末難なくしたゝめまうけて」、「年來もあればこそあれ、其の事待たん、ほどあらじ。物さわがしからぬやうに」など思はんには、えさらぬ事のみいとゞ重なりて、事の盡くる限もなく、思ひ立つ日もあるべからず。おほやう人を見るに、少し心あるきはは、皆此のあらましにてぞ一期は過ぐめる。ちかき火などに逃ぐる人は、しばしとやいふ。身を助けんとすれば、恥をも顧みず、財をも捨てて逃れ去るぞかし。命は人を待つものかは。無常の來る事は、水火のせむるよりも速に、逃れがたきものを、其の時、老いたる親、幼き子、君の恩、人の情、捨てがたしとて捨てざらんや。
第六十段
眞乘院に盛親僧都とて、やんごとなき智者ありけり。いもがしらといふ物を好みて、多く食ひけり。談義の座にても、大きなる鉢にうづだかく盛りて、膝元におきつゝ、食ひながら文をも讀みけり。患ふことあるには、七日、二七日など、療治とて籠り居て、思ふやうによきいもがしらをえらびて、殊に多く食ひて、萬の病を癒やしけり。人に食はする事なし。たゞひとりのみぞ食ひける。きはめて貧しかりけるに、師匠死にざまに、錢二百貫と坊ひとつを讓りたりけるを、坊を百貫に賣りて、彼是三萬疋をいもがしらの錢と定めて、京なる人に預けおきて、十貫づつとりよせて、芋頭を乏しからずめしけるほどに、又他用にもちふることなくて、其の錢皆になりにけり。「三百貫の物を貧しき身にまうけて、かく計ひける、誠に有り難き道心者なり」とぞ、人申しける。此の僧都、ある法師を見て、しろうるりといふ名をつけたりけり。「とは何物ぞ」と人の問ひければ、「さる物を我も知らず。若しあらましかば、此の僧の顏に似てん」とぞいひける。
この僧都、みめよく力つよく、大食にて、能書、學匠、辯説人にすぐれて、宗の法燈なれば、寺中にも重く思はれたりけれども、世をかろく思ひたる曲者にて、萬づ自由にして、大方、人にしたがふといふ事なし。出仕して饗膳などにつく時も、皆人の前据ゑわたすを待たず、我が前に据ゑぬれば、やがてひとり打食ひて、歸りたければ、ひとりついたちて行きけり。とき、非時も、人にひとしく定めて食はず、わが食ひたき時、夜なかにも曉にも食ひて、睡たければ、晝もかけこもりて、いかなる大事あれども、人のいふ事聞き入れず。目さめぬれば幾夜もいねず、心をすましてうそぶき歩きなど、尋常ならぬさまなれども、人にいとはれず、萬づゆるされけり。徳のいたれりけるにや。
第六十一段
御産の時、甑落す事は、定まれる事にはあらず、御胞衣とゞこほる時のまじなひなり。とゞこほらせ給はねば此の事なし。下ざまより事起りて、させる本説なし。大原の里のこしきを召すなり。ふるき寶藏の繪に、賤き人の子産みたる所に、甑落したるを書きたり。
第六十二段
延政門院いときなくおはしましける時、院へ參る人に御言づてとて申させ給ひける御歌、ふたつ文字牛の角文字直ぐな文字ゆがみ文字とぞ君はおぼゆるこひしく思ひ參らせ給ふとなり。
第六十三段
後七日の阿闍梨、武者を集むること、いつとかや盗人にあひにけるより、宿直人とて、かくこと/\しくなりにけり。一年の相は、此の修中の有樣にこそ見ゆなれば、兵を用ゐん事、おだやかならぬことなり。
第六十四段
車の五つ緒は、必ず人によらず、ほどにつけて、極むる官位に至りぬれば、乘るものなりとぞ、或人仰せられし。
第六十五段
此の比の冠は、昔よりは、はるかに高くなりたるなり。古代の冠桶をもちたる人は、はたをつぎて、今用ゐるなり。
第六十六段
岡本關白殿、盛りなる紅梅の枝に鳥一雙を添へて、此の枝に附けて參らすべきよし、御鷹飼下毛野武勝に仰せられたりけるに、「花に鳥つくる術、知りさふらはず、一枝に二つつくる事も存知候はず」と申しければ、膳部に尋ねられ、人々に問はせ給ひて、又武勝に、「さらば、己が思はんやうにつけて參らせよ」と仰せられたりければ、花もなき梅の枝に、一つを付けて參らせけり。
武勝が申し侍りしは、「柴の枝、梅の枝、つぼみたると散りたるとに付く。五葉などにも付く。枝の長さ七尺、或は六尺、返し刀五分にきる。枝の半に鳥を付く。付くる枝、ふまする枝あり。しゞら藤のわらぬにて、二ところ付くべし。藤のさきは、ひうち羽の長に比べてきりて、牛の角のやうに撓むべし。初雪の朝、枝を肩にかけて、中門よりふるまひて參る。大みぎりの石を傳ひて、雪に跡をつけず、あまおほひの毛を少しかなぐりちらして、二棟の御所の高欄に寄せかく。禄をいださるれば、かたにかけて、拜して退く。初雪といへども、沓のはなのかくれぬほどの雪には參らず。あまおほひの毛を散らすことは、鷹は、よわごしをとる事なれば、御鷹のとりたるよしなるべし」と申しき。
花に鳥付けずとは、いかなる故にかありけん。長月ばかりに、梅の作り枝に雉を付けて、「君がためにと折る花は、時しもわかぬ」といへる事、伊勢物語にみえたり。作り花はくるしからぬにや。
第六十七段
賀茂の岩本、橋本は、業平、實方なり。人の常にいひまがへ侍れば、一年參りたりしに、老いたる宮司の過ぎしを呼び止めて、尋ね侍りしに、「實方は、御手洗に影のうつりける所と侍れば、橋本やなほ水の近ければと覺え侍る。吉水和尚、月をめで花を眺めしいにしへのやさしき人はこゝにありはらと詠み給ひけるは、岩本の社とこそ承りおき侍れど、おのれらよりは、なか/\御存知などもこそさふらはめ」と、いとうや/\しく言ひたりしこそ、いみじくおぼえしか。
今出川院近衞とて、集どもにあまた入りたる人は、若かりける時、常に百首の歌を詠みて、かの二つの社の御前の水にて書きて手向けられけり。誠にやん事なき譽ありて、人の口にある歌多し。作文、詩序など、いみじく書く人なり。
第六十八段
筑紫に、なにがしの押領使などいふやうなる者の有りけるが、土大根を萬づにいみじき藥とて、朝毎に二つづつ燒きて食ひける事、年久しくなりぬ。或時、館の内に人もなかりける隙をはかりて、敵襲ひ來りて圍み攻めけるに、館の内に兵二人いで來て命を惜しまず戰ひて、皆追ひ返してけり。いと不思議に覺えて、「日比こゝにものし給ふとも見ぬ人々の、かく戰ひし給ふは、いかなる人ぞ」と問ひければ、「年來たのみて朝な/\めしつる土大根らにさふらう」といひて失せにけり。深く信をいたしぬれば、かゝる徳もありけるにこそ。
第六十九段
書寫の上人は、法華讀誦の功つもりて、六根淨にかなへる人なりけり。旅のかりやに立ち入られけるに、豆の殻を焚きて豆を煮ける音のつぶ/\と鳴るを聞き給ひければ、「疎からぬ己等しも、恨しく我をば煮て、辛きめを見するものかな」といひけり。焚かるゝ豆殻のはら/\と鳴る音は、「我が心よりすることかは。やかるゝはいかばかり堪へがたけれども、力なき事なり。かくな恨み給ひそ」とぞ聞えける。
第七十段
元應の清暑堂の御遊に、玄上は失せにし比、菊亭大臣、牧馬を彈じ給ひけるに、座に著きて、先づ柱を探られたりければ、一つ落ちにけり。御懷にそくひを持ち給ひたるにて付けられにければ、神供の參る程によく干て、ことゆゑなかりけり。いかなる意趣かありけん、物見ける衣かづきの寄りて、放ちて、もとのやうにおきたりけるとぞ。
第七十一段
名を聞くより、やがて面影はおしはからるゝ心地するを、見る時は、又かねて思ひつるまゝの顏したる人こそなけれ。昔物語を聞きても、此の比の人の家のそこほどにてぞありけんと覺え、人も、今見る人の中に思ひよそへらるゝは、誰もかく覺ゆるにや。又如何なる折ぞ、只今人の云ふ事も、目に見ゆる物も、わが心のうちも、かゝる事のいつぞや有りしがと覺えて、いつとは思ひ出でねども、まさしく有りし心地のするは、我ばかりかく思ふにや。
第七十二段
賤しげなるもの。居たるあたりに調度の多き。硯に筆の多き。持佛堂に佛の多き。前栽に石、草木の多き。家の内に子孫の多き。人に逢ひて詞の多き。願文に作善多く書きのせたる。多くて見苦しからぬは、文車の文、塵塚の塵。
第七十三段
世に語り傳ふる事、まことはあいなきにや、多くは皆虚言なり。あるにも過ぎて人は物を言ひなすに、まして年月過ぎ、境もへだたりぬれば、言ひたきまゝに語りなして、筆にも書きとゞめぬれば、やがて又定まりぬ。道々の物の上手のいみじき事など、かたくななる人の其の道知らぬは、そゞろに神のごとくに言へども、道知れる人は更に信も起さず。音に聞くと見る時とは、何事も變るものなり。かつあらはるゝをもかへりみず、口にまかせて言ひちらすは、やがて浮きたることと聞ゆ。又我も誠しからずは思ひながら、人のいひしまゝに、鼻のほどおごめきていふは、其の人のそらごとにはあらず。げに/\しくところ/\うちおぼめき、よく知らぬよしして、さりながらつま/\あはせて語るそらごとは、恐しきなり。わがため面目あるやうに言はれぬるそらごとは、人いたくあらがはず。皆人の興ずる虚言は、ひとり「さもなかりしものを」といはんも詮なくて、聞きゐたるほどに、證人にさへ
なされて、いとゞ定まりぬべし。とにもかくにも、そらごと多き世なり。たゞ常に有るめづらしからぬ事のまゝに心得たらん、よろづ違ふべからず。下ざまの人の物語は、耳おどろく事のみあり。よき人は、あやしき事を語らず。かくはいへど、佛神の奇特、權者の傳記、さのみ信ぜざるべきにもあらず。これは、世俗の虚言をねんごろに信じたるもをこがましく、「よもあらじ」などいふも詮なければ、大方は誠しくあひしらひて、偏に信ぜず、また疑ひ嘲るべからず。
第七十四段
蟻の如くに集りて、東西にいそぎ、南北に走る。高きあり、賤しきあり。老いたるあり、若きあり。行く所あり、歸る家あり。夕にいねて、朝に起く。いとなむ所何事ぞや。生を貪り、利を求めて止む時なし。身を養ひて何事をか待つ。期する所、たゞ老と死とにあり。其の來る事速にして、念々の間にとゞまらず。是を待つ間、何のたのしびかあらん。惑へる者はこれを恐れず、名利におぼれて先途の近き事をかへりみねばなり。おろかなる人は、またこれを悲しぶ。常住ならんことを思ひて變化の理を知らねばなり。
第七十五段
つれ/\わぶる人は、いかなる心ならん。まぎるゝかたなく、たゞひとりあるのみこそよけれ。
世にしたがへば、心、外の塵にうばはれて惑ひやすく、人に交れば、言葉よその聞きに隨ひて、さながら心にあらず。人に戲れ、物に爭ひ、一度は恨み、一度は喜ぶ。其の事定まれる事なし。分別みだりに起りて、得失やむ時なし。惑の上に醉へり。醉の中に夢をなす。走りていそがはしく、ほれて忘れたる事、人皆かくの如し。いまだ誠の道を知らずとも、縁をはなれて身を閑かにし、ことにあづからずして心をやすくせんこそ、暫く樂しぶともいひつべけれ。「生活、人事、伎能、學問等の諸縁をやめよ」とこそ、摩訶止觀にも侍れ。
第七十六段
世の覺え花やかなるあたりに、嘆も喜もありて、人おほく行きとぶらふ中に、ひじり法師のまじりて、いひ入れたゝずみたるこそ、さらずともと見ゆれ。さるべき故有りとも、法師は人にうとくてありなん。
第七十七段
世の中にその比人のもてあつかひぐさにいひあへる事、いろふべきにはあらぬ人の、よく案内知りて、人にも語り聞かせ、問ひ聞きたるこそうけられね。ことに片邊なるひじり法師などぞ、世の人の上は、わが如く尋ね聞き、いかでかばかりは知りけんと覺ゆるまでぞ、言ひちらすめる。
第七十八段
今樣の事どもの珍しきをいひ廣めもてなすこそ、又うけられね。世にことふりたるまで知らぬ人は心にくし。いまさらの人などのある時、こゝもとにいひつけたることぐさ、物の名など、心得たるどち、片はし言ひ交し、目見あはせ、笑ひなどして、心知らぬ人に、心えずおもはする事、世なれず、よからぬ人の、必ずある事なり。
第七十九段
何事も入りたゝぬさましたるぞよき。よき人は、知りたる事とて、さのみ知りがほにやは言ふ。片田舎よりさし出でたる人こそ、萬の道に心得たるよしのさしいらへはすれ。されば、世にはづかしきかたもあれど、みづからもいみじと思へるけしき、かたくななり。よくわきまへたる道には、必ず口おもく、問はぬ限は言はぬこそいみじけれ。
第八十段
人ごとに、我が身にうとき事をのみぞ好める。法師は兵の道をたて、夷は弓ひく術知らず、佛法知りたる氣色し、連歌し、管絃を嗜みあへり。されど、おろかなる己が道よりは、なほ人におもひ侮られぬべし。法師のみにもあらず、上達部、殿上人、かみざままで、おしなべて武を好む人多かり。百度戰ひて百度勝つとも、いまだ武勇の名を定めがたし。其の故は、運に乘じてあだをくだく時、勇者にあらずといふ人なし。兵盡き矢きはまりて、遂に敵に降らず、死をやすくして後、始めて名をあらはすべき道なり。生けらんほどは、武に誇るべからず。人倫に遠く禽獸に近き振舞、其の家にあらずば、好みて益なきことなり。
第八十一段
屏風、障子などの繪も文字も、かたくななる筆やうして書きたるが見にくきよりも、宿の主のつたなく覺ゆるなり。大方持てる調度にても、心劣りせらるゝ事は有りぬべし。さのみよき物を持つべしとにもあらず。損ぜざらんためとてしななく見にくきさまにしなし、珍しからんとて用なきことどもし添へ、わづらはしく好みなせるをいふなり。古めかしきやうにて、いたくこと/\しからず、費もなくて、物がらのよきがよきなり。
第八十二段
「うすものの表紙は、とく損ずるがわびしき」と人のいひしに、頓阿が、「羅は上下はづれ、螺鈿の軸は貝落ちて後こそいみじけれ」と申し侍りしこそ、心まさりて覺えしか。一部とある草子などの、おなじやうにもあらぬを見にくしといへど、弘融僧都が、「物を必ず一具にとゝのへんとするは、つたなき者のする事なり。不具なるこそよけれ」といひしも、いみじく覺えしなり。すべて何も皆、ことの整ほりたるはあしき事なり。し殘したるを、さて打置きたるは、面白く、生き延ぶるわざなり。「内裏造らるゝにも、必ず作りはてぬ所を殘す事なり」と或人申し侍りし也。先賢のつくれる内外の文にも、章段の缺けたる事のみこそ侍れ。
第八十三段
竹林院入道左大臣殿、太政大臣にあがり給はんに何の滯りかおはせんなれども、「珍しげなし、一上にてやみなん」とて、出家し給ひにけり。洞院左大臣殿、此の事を甘心し給ひて、相國の望おはせざりけり。「亢龍の悔あり」とかやいふ事侍るなり。月滿ちては缺け、物盛りにしては衰ふ。萬の事、さきのつまりたるは、破に近き道なり。
第八十四段
法顯三藏の、天竺にわたりて、故郷の扇を見ては悲しび、病に臥しては漢の食を願ひ給ひける事を聞きて、「さばかりの人の、無下にこそ心弱き氣色を、人の國にてみえ給
ひけれ」と人のいひしに、弘融僧都、「優に情有りける三藏かな」といひたりしこそ、法師のやうにもあらず心にくゝ覺えしか。
第八十五段
人の心すなほならねば、僞なきにしもあらず。されどもおのづから正直の人、などかなからん。己すなほならねど、人の賢を見てうらやむは尋常なり。至りておろかなる人は、たま/\賢なる人を見て、是を憎む。「大きなる利を得んがために少しきの利をうけず、僞りかざりて名をたてんとす」とそしる。己が心に違へるによりて、此の嘲をなすにて知りぬ、此の人は下愚の性うつるべからず、僞りて小利をも辭すべからず、かりにも賢を學ぶべからず。狂人のまねとて大路を走らば、則ち狂人なり。惡人のまねとて人を殺さば、惡人なり。驥を學ぶは驥の類、舜を學ぶは舜の徒なり。僞りても賢を學ばんを賢といふべし。
第八十六段
惟繼中納言は、風月の才に富める人なり。一生精進にて、讀經うちして、寺法師の圓伊僧正と同宿して侍りけるに、文保に三井寺燒かれし時、坊主にあひて、「御坊をば寺法師とこそ申しつれど、寺はなければ、今よりは法師とこそ申さめ」といはれけり。いみじき秀句なりけり。
第八十七段
下部に酒飲まする事は、心すべきことなり。宇治に住み侍りける男、京に具覺房とて、なまめきたる遁世の僧を、こじうとなりければ、常に申し睦びけり。或時、迎へに馬を遣はしたりければ、「遙なるほどなり。口づきの男に、先づ一度せさせよ」とて、酒を出だしたれば、さしうけ/\よゝと飲みぬ。太刀うちはきて、かひ/\しげなれば、たのもしく覺えて、召し具して行くほどに、木幡のほどにて、奈良法師の兵士あまた具してあひたるに、此の男立ちむかひて、「日暮れにたる山中に、あやしきぞ、とまり候へ」といひて、太刀を引拔きければ、人も皆、太刀拔き矢はげなどしけるを、
具覺房手をすりて、「うつし心なく醉ひたる者に候。まげて許し給はらん」といひければ、各嘲りて過ぎぬ。此の男具覺房にあひて、「御房は口惜しき事し給ひつるものかな。おのれ醉ひたる事侍らず。高名仕らんとするを、拔ける太刀むなしくしなし給ひつること」と怒りて、ひたぎりに斬り落しつ。さて、「山だち有り」とのゝしりければ、里人おこりていであへば、「我こそ山だちよ」といひて、走りかゝりつゝ斬り廻りけるを、あまたして、手負ほせ、打ちふせて縛りけり。馬は血つきて、宇治大路の家に走り入りたり。あさましくて、男共あまた走らかしたれば、具覺房は、くちなし原にによび伏したるを、求め出でてかきもてきつ。辛き命生きたれど、腰斬り損ぜられて、かたはになりにけり。
第八十八段
或者、小野道風の書ける和漢朗詠集とて持ちたりけるを、或人、「御相傳、うける事には侍らじなれども、四條大納言撰ばれたる物を、道風書かん事、時代や違ひ侍らん、覺束なくこそ」といひければ、「さ候へばこそ、世に有難き物には侍りけれ」とて、いよいよ秘藏しけり。
第八十九段
「奥山に猫またといふものありて、人を食ふなる」と、人のいひけるに、「山ならねども、これらにも猫の經上りて、猫またになりて、人とる事はあなるものを」と云ふ者有りけるを、何阿彌陀佛とかや、連歌しける法師の行願寺の邊にありけるが聞きて、ひとり歩かん身は心すべき事にこそと思ひける比しも、或所にて夜更くるまで連歌して、たゞひとり歸りけるに、小川のはたにて、音に聞きし猫また、あやまたず足許へふと寄りきて、やがて掻きつくまゝに、頸のほどを食はんとす。肝心も失せて、防がんとするに力もなく、足も立たず、小川へ轉び入りて、「たすけよや、ねこまた、よやよや」と叫べば、家々より、松どもともして走り寄りて見れば、このわたりに見知れる僧なり。「こは如何に」とて、川の中より抱き起したれば、連歌のかけもの取りて、扇、小箱など懷に持ちたりけるも、水に入りぬ。希有にして助りたるさまにて、はふはふ家に入りにけり。飼ひける犬の、暗けれど主を知りて、飛付きたりけるとぞ。
第九十段
大納言法印の召使ひし乙鶴丸、やすら殿といふ者を知りて、常に行通ひしに、或時出でて帰り來たるを、法印、「いづくへ行きつるぞ」と問ひしかば、「やすら殿のがり罷りて候」といふ。「其のやすら殿は、男か法師か」と又問はれて、袖かきあはせて、「いかゞ候らん、頭をば見候はず」と答へ申しき。などか、頭ばかりの見えざりけん。
第九十一段
赤舌日といふ事、陰陽道には沙汰なき事なり。昔の人是を忌まず。此の比、何者のいひいでて忌み始めけるにか、此の日ある事、末とほらずといひて、其の日いひたりしこと、したりしこと、かなはず、えたりし物は失ひつ、企てたりし事成らずといふ、おろかなり。吉日を選びてなしたるわざの、すゑとほらぬを數へてみんも、又ひとしかるべし。その故は、無常變易のさかひ、有りと見るものも存せず、始ある事も終なし。志は遂げず、望は絶えず。人の心不定なり、物皆幻化なり。何事か暫くも住する。此の理を知らざるなり。吉日に惡をなすに必ず凶なり、惡日に善を行ふに必ず吉なりといへり。吉凶は人によりて、日によらず。
第九十二段
或人、弓射る事を習ふに、もろ矢をたばさみて的にむかふ。師の云はく、「初心の人、ふたつの矢をもつ事なかれ。後の矢を頼みて、はじめの矢に等閑の心あり。毎度たゞ得失なく、此の一矢に定むべしと思へ」といふ。僅かに二つの矢、師の前にて、一つをおろかにせんと思はんや。懈怠の心、みづから知らずといへども、師是を知る。此のいましめ、萬事にわたるべし。道を學する人、夕には朝あらん事を思ひ、朝には夕あらん事を思ひて、重ねてねんごろに修せんことを期す。況んや、一刹那のうちにおいて、懈怠の心有る事を知らんや。何ぞ只今の一念において、直ちにする事の甚だ難き。
第九十三段
「牛を賣る者あり。買ふ人、明日その値をやりて牛をとらんといふ。夜の間に牛死ぬ。買はんとする人に利あり、賣らんとする人に損あり」と語る人あり。是を聞きて、かたへなる者の云はく、「牛の主誠に損有りといへども、又大きなる利あり。其の故は、生ある者、死のちかき事を知らざる事、牛既に然なり。人又同じ。はからざるに牛は死し、はからざるに主は存ぜり。一日の命、萬金よりも重し。牛の値鵞毛よりも輕し。萬金を得て一錢を失はん人、損ありといふべからず」といふに、皆人嘲りて、「其の理は牛の主に限るべからず」といふ。又云はく、「されば、人死を憎まば、生を愛すべし。存命の喜、日々に樂しまざらんや。おろかなる人、此の樂を忘れて、いたづがはしく外の樂しびを求め、此の財を忘れて、危く他の財を貪るには、志滿つ事なし。行ける間生を樂しまずして、死に臨みて死をおそれば、此の理あるべからず。人皆生を樂しまざるは、死をおそれざる故なり。死をおそれざるにはあらず。死の近き事を忘るゝなり。もし又、生死の相にあづからずといはば、實の理を得たりといふべし」といふに、人いよ/\あざける。
第九十四段
常磐井相國、出仕し給ひけるに、勅書を持ちたる北面あひ奉りて、馬よりおりたりけるを、相國後に、「北面なにがしは、勅書を持ちながら下馬し侍りし者なり。かほどの者、いかでか君につかうまつり候べき」と申されければ、北面をはなたれにけり。勅書を、馬の上ながらさゝげて見せ奉るべし、おるべからずとぞ。
第九十五段
「箱のくりかたに緒を付くる事、いづかたに付け侍るべきぞ」と、ある有職の人に尋ね申し侍りしかば、「軸に付け、表紙に付くる事、兩説なればいづれも難なし。文の箱は、多くは右に付く。手箱には軸に付くるも常の事なり」と仰せられき。
第九十六段 めなもみといふ草有り。くちばみにさゝれたる人、かの草をもみて付けぬれば、則ち癒ゆとなん。見知りておくべし。
第九十七段
其の物につきて、其の物を費しそこなふ物、數を知らずあり。身に虱あり、家に鼠あり、國に賊あり、小人に財あり、君子に仁義あり、僧に法あり。
第九十八段
尊きひじりの云ひ置きける事を書き付けて、一言芳談とかや名付けたる草子を見侍りしに、心にあひて覺えし事ども。
一、しやせまし、せずやあらましと思ふ事は、おほやうは、せぬはよきなり。
一、後世を思はん者は糂汰瓶一つも持つまじきことなり。持經、本尊に至るまで、よき物をもつ、よしなき事なり。
一、遁世者は、なきにことかけぬやうを計らひて過ぐる、最上のやうにてあるなり。
一、上臈は下臈になり、智者は愚者になり、徳人は貧になり、能ある人は無能になるべきなり。
一、佛道をねがふといふは別の事なし。暇ある身になりて、世の事を心にかけぬを、第一の道とす。
此の外もありし事どもおぼえず。
第九十九段
堀川相國は、美男のたのしき人にて、そのこととなく過差を好み給ひけり。御子基俊卿を大理になして、廳務おこなはれけるに、廳屋の唐櫃見苦しとて、めでたく作り改めらるべき由仰せられけるに、此の唐櫃は上古より傳はりて、其の始を知らず、數百年を經たり。累代の公物、古弊をもちて規模とす。たやすく改められがたき由、故實の諸官等申しければ、其の事やみにけり。
第百段
久我相國は、殿上にて水を召しけるに、主殿司、土器を奉りければ、「まがりを參らせよ」とて、まがりしてぞ召しける。
第百一段 或人、任大臣の節會の内辨をつとめられけるに、内記の持ちたる宣命をとらずして、堂上せられにけり。きはまりなき失禮なれども、立ち歸りとるべきにもあらず、思ひ患はれけるに、六位外記康綱、衣かづきの女房を語らひて、彼の宣命をもたせて、忍びやかに奉らせけり。いみじかりけり。
第百二段 尹大納言光忠入道、追儺の上卿を務められけるに、洞院右大臣殿に次第を申し請けられければ、「又五郎男を師とするより外の才覺候はじ」とぞのたまひける。かの又五郎は、老いたる衞士の、よく公事に馴れたる者にてぞありける。近衞殿、著陣し給ひける時、軾を忘れて、外記を召されければ、火焚きて候ひけるが、「先づ軾をめさるべくや候ふらん」と忍びやかにつぶやきける、いとをかしかりけり。
第百三段 大覺寺殿にて、近習の人ども、なぞ/\を作りてとかれける處へ、醫師忠守參りたりけるに、侍從大納言公明卿、「我が朝の者とも見えぬ忠守かな」となぞ/\にせられにけるを、「唐瓶子」と解きて笑ひ合はれければ、腹立ちて退り出でにけり。
第百四段
荒れたる宿の人目なきに、女の憚る事ある比にて、つれ/\と籠り居たるを、或人とぶらひたまはんとて、夕月夜の覺束なきほどに、忍びて尋ねおはしたるに、犬のことごとしくとがむれば、げす女の出でて、「いづくよりぞ」といふに、やがて案内せさせて入り給ひぬ。心細げなる有樣、いかで過ぐすらんと、いと心ぐるし。あやしき板敷にしばし立ち給へるを、もてしづめたる氣配の、若やかなるして、「こなた」といふ人あれば、たてあけ所せげなる遣戸よりぞ入り給ひぬる。内のさまは、いたくすさまじからず。心にくゝ火はあなたにほのかなれど、もののきらなど見えて、俄にしもあらぬにほひ、いとなつかしうすみなしたり。「門よくさしてよ。雨もぞふる、御車は門のしたに、御供の人はそこ/\に」といへば、「こよひぞやすき寢は寢べかめる」と打さゝめくも、忍びたれど、ほどなければ、ほのきこゆ。さて、此のほどの事どもこまやかにきこえ給ふに、夜深き鳥も鳴きぬ。來し方行末かけて、まめやかなる御物語に、此の度は鳥も花やかなる聲にうちしきれば、明けはなるゝにやと聞き給へど、夜深く急ぐべき所の樣にもあらねば、少したゆみ給へるに、隙しろくなれば、忘れがたき事などいひて、立ち出で給ふに、梢も庭もめづらしく青みわたりたる卯月ばかりのあけぼの、艶にをかしかりしをおぼし出でて、桂の木の大きなるが隱るゝまで、いまも見送り給ふとぞ。
第百五段
北の屋かげに消え殘りたる雪のいたう凍りたるに、さし寄せたる車のながえも、霜いたくきらめきて、有明の月さやかなれども、くまなくはあらぬに、人離れたる御堂の廊に、なみ/\にはあらずと見ゆる男、女となげしにしりかけて物語するさまこそ、何事にかあらん、つきすまじけれ。かぶし、かたちなどいとよしと見えて、えもいはぬにほひの、さとかをりたるこそをかしけれ。氣配など、はつれ/\きこえたるもゆかし。
第百六段
高野の證空上人、京へのぼりけるに、細道にて、馬に乘りたる女の行きあひたりけるが、口ひきける男、あしくひきて、聖の馬を堀へ落してけり。聖いと腹惡しくとがめて、「こは希有の狼藉かな。四部の弟子はよな、比丘よりは比丘尼は劣り、比丘尼より優婆塞は劣り、優婆塞より優婆夷は劣れり。かくの如くの優婆夷などの身にて、比丘を堀へ蹴入れさする、未曾有の惡行なり」といはれければ、口ひきの男、「いかに仰せらるゝやらん、えこそ聞きしらね」といふに、上人なほいきまきて、「何といふぞ、非修非學の男」と、あらゝかにいひて、きはまりなき放言しつと思ひける氣色にて、馬ひき返して逃げられにけり。たふとかりけるいさかひなるべし。
第百七段
女の物言ひかけたる返事、とりあへずよきほどにする男は有り難きものぞとて、龜山院の御時、しれたる女房ども、若き男達の參らるゝ毎に、「郭公や聞き給へる」と問ひて試みられけるに、なにがしの大納言とかやは、「數ならぬ身はえ聞き候はず」と答へられけり。堀川内大臣殿は、「岩倉にて聞きて候ひしやらん」と仰せられたりけるを、「是は難なし。數ならぬ身、むつかし」など定め合はれけり。すべて男をば、女に笑はれぬやうにおほしたつべしとぞ。「淨土寺前關白殿は、幼くて、安喜門院のよく教へ參らせさせ給ひける故に、御詞などのよきぞ」と、人の仰せられけるとかや。山階左大臣殿は、「あやしの下女の見奉るも、いとはづかしく、心づかひせらるゝ」とこそ仰せられけれ。女のなき世なりせば、衣文も冠も、いかにもあれ、ひきつくろふ人も侍らじ。かく人にはぢらるゝ女、如何ばかりいみじきものぞと思ふに、女の性は皆ひがめり。人我の相深く、貪欲甚だしく、物の理を知らず。たゞ迷の方に心も早く移り、詞も巧に、苦しからぬ事をも問ふ時は言はず。用意有るかとみれば、又あさましき事まで問はず語りに言ひ出す。深くたばかりかざれる事は、男の智慧にもまさりたるかと思へば、其の事跡よりあらはるゝを知らず。すなほならずして、拙きものは女なり。其の心に隨ひてよく思はれん事は、心うかるべし。されば、何かは女のはづかしからん。もし賢女あらば、それも物うとく、すさまじかりなん。たゞ迷をあるじとしてかれにしたがふ時、やさしくも面白くも覺ゆべき事なり。
第百八段
寸陰惜しむ人なし。これよく知れるか、おろかなるか。おろかにして怠る人のために言はば、一錢輕しといへども、是を重ぬれば、貧しき人を富める人となす。されば、商人の一錢を惜しむ心切なり。刹那覺えずといへども、これをはこびてやまざれば、命を終ふる期忽に至る。されば道人は、とほく日月を惜しむべからず。只今の一念、空しく過ぐる事を惜しむべし。若し人來りて、我が命、明日は必ず失はるべしと告げ知らせたらんに、今日の暮るゝ間、何事をか頼み、何事をか營まん。我等が生ける今日の日、何ぞ其の時節に異な
らん。一日のうちに、飲食、便利、睡眠、言語、行歩、止む事を得ずして多くの時を失ふ。其の餘りの暇幾ばくならぬうちに、無益の事をなし、無益の事をいひ、無益の事を思惟して時を移すのみならず、日を消し、月を亙りて一生を送る、尤もおろかなり。謝靈運は法華の筆受なりしかども、心常に風雲の思を觀ぜしかば、慧遠白蓮の交を許さざりき。暫くもこれなき時は、死人に同じ。光陰何のためにか惜しむとならば、内に思慮なく、外に世事なくして、止まん人は止み、修せん人は修せよとなり。
第百九段
高名の木のぼりといひし男、人をおきてて、高き木にのぼせて梢をきらせしに、いと危くみえしほどはいふ事もなくて、おるゝ時に、軒長ばかりになりて、「あやまちすな、心しておりよ」と言葉をかけ侍りしを、「かばかりになりては、飛びおるゝともおりなん、如何にかくいふぞ」と申し侍りしかば、「其の事に候。目くるめき、枝危きほどは、己が恐れ侍れば申さず。あやまちは、やすき所になりて、必ず仕る事に候」といふ。あやしき下臈なれども、聖人の戒にかなへり。鞠も、難き所を蹴出して後、やすく思へば、必ず落つと侍るやらん。
第百十段
雙六の上手といひし人に、其の行を問ひ侍りしかば、「勝たんとうつべからず。負けじとうつべきなり。いづれの手か疾く負けぬべきと案じて、その手をつかはずして、一めなりとも、おそく負くべき手につくべし」といふ。道を知れる教、身を治め、國を保たん道も、又しかなり。
第百十一段
「圍棊、雙六好みてあかしくらす人は、四重五逆にもまされる惡事とぞ思ふ」と、或ひじりの申しし事、耳にとゞまりて、いみじく覺え侍る。
第百十二段
明日は遠國へ赴くべしときかん人に、心閑かになすべからんわざをば、人言ひかけてんや。俄の大事をも營み、切に嘆く事もある人は、他の事を聞き入れず、人の愁、喜をもとはず、とはずとて、などやと恨むる人もなし。されば、年もやう/\闌け、病にもまつはれ、況んや世をも遁れたらん人、又是に同じかるべし。人間の儀式、いづれの事か去り難からぬ。世俗のもだしがたきに隨ひてこれを必ずとせば、願も多く、身も苦しく、心の暇もなく、一生は雜事の小節にさへられて空しく暮れなん。日暮れ塗遠し。吾が生既に蹉だたり。諸縁を放下すべき時なり。信をも守らじ、禮儀をも思はじ。此の心をも得ざらん人は、物狂ともいへ、うつゝなし、情なしとも思へ。毀るとも苦しまじ、譽むとも聞き入れじ。
第百十三段
四十に餘りぬる人の、色めきたる方、おのづから、忍びてあらんはいかゞはせん。ことに打出でて、男女の事、人のうへをも言ひたはぶるゝこそ、にげなく、見苦しけれ。大方、聞きにくゝ見苦しき事、老人の若き人に交りて、興あらんと物言ひゐたる、數ならぬ身にて、世の覺えある人をへだてなき樣にいひたる、貧しき所に、酒宴好み、客人に饗應せんときらめきたる。
第百十四段
今出川のおほい殿、嵯峨へおはしけるに、有栖川のわたりに、水の流れたる所にて、さい王丸御牛を追ひたりければ、あがきの水、前板までさゝとかゝりけるを、爲則御車のしりに候ひけるが、「希有の童かな。かゝる所にて、御牛をばおふものか」といひたりければ、おほい殿御氣色惡しくなりて、「おのれ車遣らん事、さい王丸にまさりて得知らじ。希有の男なり」とて、御車に頭をうちあてられにけり。この高名のさい王丸は、太秦殿の男、料の御牛飼ぞかし。此の太秦殿に侍りける女房の名ども、一人はひざさち、一人はことづち、一人ははふばら、一人はおとうしとつけられけり。
第百十五段
宿河原といふ所にて、ぼろ/\おほく集まりて、九品の念佛を申しけるに、外より入り來たるぼろ/\の、「もし此の御中に、いろをし房と申すぼろやおはします」と尋ねければ、其の中より、「いろをしこゝに候ふ。かくのたまふは誰そ」と答ふれば、「しら梵字と申す者なり。おのれが師なにがしと申しし人、東國にて、いろをしと申すぼろに殺されけりと承りしかば、その人にあひ奉りて、恨み申さばやと思ひて、尋ね申すなり」とふ。いろをし、「ゆゝしくも尋ねおはしたり。さる事侍りき。こゝにて對面し奉らば、道場をけがし侍るべし。前の河原へ參りあはん。あなかしこ、わきざしたち、いづかたをもみつぎ給ふな。あまたのわづらひにならば、佛事の妨に侍るべし」といひ定めて、二人河原へ出であひて、心行くばかりに貫ぬき合ひて、共に死ににけり。ぼろ/\といふもの、昔はなかりけるにや。近き世に、ぼろんじ、梵字、漢字など云ひける者、其の始なりけるとかや。世を捨てたるに似て、我執深く、佛道を願ふに似て、鬪諍をこととす。放逸無慚の有樣なれども、死を輕くして、少しもなづまざる方のいさぎよく覺えて、人の語りしまゝに書き付け侍るなり。
第百十六段
寺院の號、さらぬ萬の物にも、名をつくる事、昔の人は、少しも求めず、たゞありのまゝに、やすく付けけるなり。此の比は、深く案じ、才覺をあらはさんとしたるやうにきこゆる、いとむつかし。人の名も、めなれぬ文字をつかんとする、益なき事なり。何事も、珍しき事を求め異説を好むは、淺才の人の必ずある事なりとぞ。
第百十七段
友とするにわろき者七つあり。一つには高くやん事なき人、二つには若き人、三つには病なく身強き人、四つには酒を好む人、五つには武く勇める兵、六つには虚言する人、七つには欲ふかき人。よき友三つあり。一つには物くるゝ友。二つには醫師、三つには智惠ある友。
第百十八段 鯉のあつもの食ひたる日は、鬢そゝけずとなん。膠にもつくるものなれば、ねばりたるものにこそ。鯉ばかりこそ、御前にても切らるゝ物なれば、やん事なき魚なり。鳥には雉、さうなき物なり。雉、松茸などは、御湯殿の上にかゝりたるも苦しからず。其の外は心うき事なり。中宮の御方の御湯殿の上のくろみ棚に、雁の見えつるを、北山入道殿の御覧じて歸らせ給ひて、やがて御文にて、「かやうの物、さながら其の姿にて御棚にゐて候ひし事、見ならはず、さまあしき事なり。はか/\しき人のさふらはぬ故にこそ」など申されたりけり。
第百十九段
鎌倉の海に、かつをと云ふ魚は、彼のさかひには雙なきものにて、此の比もてなすものなり。それも、鎌倉の年寄の申し侍りしは、「此の魚、己等若かりし世までは、はか/\しき人の前へ出づること侍らざりき。頭は下部も食はず、切りて捨て侍りしものなり」と申しき。かやうの物も、世の末になれば、上ざままでも入りたつわざにこそ侍れ。
第百二十段
唐の物は、藥の外は、なくとも事缺くまじ。書どもは、此の國に多く廣まりぬれば、書きも寫してん。唐土舟のたやすからぬ道に、無用の物どものみ取りつみて、所狹く渡しもてくる、いとおろかなり。「遠き物を寶とせず」とも、又「得がたき貨を尊まず」とも、文にも侍るとかや。
第百二十一段 養ひ飼ふものには馬、牛。つなぎ苦しむるこそいたましけれど、なくてかなはぬ物なれば、いかゞはせん。犬は、まもりふせぐつとめ、人にもまさりたれば、必ず有るべし。されど家毎にある物なれば、殊更に求め飼はずともありなん。其の外の鳥獸、すべて用なきものなり。走る獸は檻にこめ、鎖をさゝれ、飛ぶ鳥は翅をきり、籠に入れられて、雲を戀ひ、野山をおもふ愁止む時なし。其の思、我が身にあたりて忍びがたくは、心あらん人、是を樂しまんや。生を苦しめて目を喜ばしむるは、桀紂が心なり。王子猷が鳥を愛せし、林に樂しぶを見て、逍遙の友としき。捕へ苦しめたるにあらず。「凡そ珍しき禽、あやしき獸、國に育はず」とこそ、文にも侍るなれ。
第百二十二段
人の才能は、文あきらかにして、聖の教を知れるを第一とす。次には手書く事、むねとする事はなくとも、是を習ふべし。學問に便あらんためなり。次に、醫術を習ふべし。身を養ひ、人を助け、忠孝のつとめも、醫にあらずは有るべからず。次に弓射、馬に乘る事、六藝に出せり。必ず是をうかがふべし。文武醫の道、誠に缺けてはあるべからず。これを學ばんをば、徒らなる人といふべからず。次に食は人の天なり。よく味を調へ知れる人、大きなる徳とすべし。次に細工、萬に要おほし。此の外の事ども、多能は君子のはづる所なり。詩歌に巧に、絲竹に妙なるは幽玄の道、君臣これを重くすといへども、今の世には、これをもちて世を治むる事、漸くおろかなるに似たり。金はすぐれたれども、鐵の益多きにしかざるが如し。
第百二十三段
無益のことをなして時を移すを、おろかなる人とも、僻事する人とも云ふべし。國のため君のために、止むことを得ずしてなすべき事多し。其の餘りの暇幾ばくならず。思ふべし、人の身に止むことをえずして營む所、第一に食ふ物、第二に著る物、第三に居る所なり。人間の大事、此の三つには過ぎず。饑ゑず、寒からず、風雨におかされずして、閑かに過ぐすを樂とす。但し人皆病あり。病におかされぬれば、其の愁忍びがたし。醫療を忘るべからず。藥を加へて、四つの事、求め得ざるを貧しとす。此の四つ缺けざるを富めりとす。此の四つの外を求め營むを驕とす。四つの事、儉約ならば、誰の人か足らずとせん。
第百二十四段
是法法師は、淨土宗にはぢずといへども、學匠をたてず、たゞ明暮念佛して、やすらかに世を過ぐす有樣、いとあらまほし。
第百二十五段
人におくれて、四十九日の佛事に、或聖を請じ侍りしに、説法いみじくして、皆人涙をながしけり。導師歸りて後、聽聞の人ども、「いつよりも、ことに今日はたふとく覺え侍りつる」と感じあへりし返事に、或者の云はく、「何とも候へ、あれほど唐の狗に似候ひなんうへは」といひたりしに、あはれもさめてをかしかりけり。さる導師のほめやうやはあるべき。又、「人に酒すゝむるとて、己まづたべて、人に強ひ奉らんとするは、劔にて人を斬らんとするに似たる事なり。二方に、刀つきたるものなれば、もたぐる時、先づ我が頸を斬る故に、人をばえ斬らぬなり。己まづ醉ひてふしなば、人はよもめさじ」と申しき。劔にて斬り試みたりけるにや、いとをかしかりき。
第百二十六段
「ばくちの負極まりて、殘りなくうちいれんとせんにあひては、うつべからず。たちかへり、續けて勝つべき時の至れると知るべし。其の時を知るを、よきばくちといふなり」と、或者申しき。
第百二十七段
あらためて益なき事は、あらためぬをよしとするなり。
第百二十八段
雅房大納言は、才賢く、よき人にて、大將にもなさばやとおぼしける比、院の近習なる人、「たゞ今あさましき事を見侍りつ」と申されければ、「何事ぞ」と問はせ給ひけるに、「雅房卿、鷹に飼はんとて、生きたる犬の足を斬り侍りつるを、中牆の穴より見侍りつ」と申されけるに、疎ましく憎くおぼしめして、日來の御氣色も違ひ、昇進もし給はざりけり。さばかりの人、鷹をもたれたりけるは思はずなれど、犬の足はあとなき事なり。虚言は不便なれども、かゝる事を聞かせ給ひて、憎ませ給ひける君の御心は、いとたふとき事なり。大方生ける物を殺し、痛めたゝかはしめて、あそび樂しまん人は、畜生殘害の類なり。萬の鳥獸、小さき蟲までも、心をとめて有樣を見るに、子を思ひ、親をなつかしくし、夫婦を伴ひ、嫉み怒り、欲多く、身を愛し、命を惜しめること、ひとへに愚癡なるゆゑに、人よりもまさりて甚だし。彼に苦しみを與へ、命を奪はん事、いかでかいたましからざらん。すべて一切の有情を見て慈悲の心なからんは、人倫にあらず。
第百二十九段 顏囘は、志、人に勞をほどこさじとなり。すべて人を苦しめ、物を虐ぐる事、賤しき民の志をも奪ふべからず。又、いときなき子をすかし、おどし、いひはづかしめて興ずる事あり。おとなしき人は、まことならねば、事にもあらず思へど、幼き心には、身にしみて恐しく、恥づかしく、あさましき思、誠に切なるべし。是をなやまして興ずる事、慈悲の心にあらず。おとなしき人の、喜び、怒り、悲しび、樂しぶも、皆虚妄なれども、誰か實有の相に著せざる。身をやぶるよりも、心をいたましむるは、人を害ふ事なほ甚だし。病をうくる事も、多くは心より受く。外より來る病は少し。藥をのみて汗を求むるには、効なきことあれども、一旦恥ぢおそるゝことあれば、必ず汗をながすは、心のしわざなりといふことを知るべし。凌雲の額を書きて、白頭の人となりしためしなきにあらず。
第百三十段
物に爭はず、己を枉げて人に從ひ、我が身を後にして人を先にするには如かず。萬の遊にも、勝負を好む人は、勝ちて興あらんためなり。己が藝の勝りたる事を喜ぶ。されば、負けて興なく覺ゆべき事、又知られたり。我負けて人を喜ばしめんと思はば、更に遊の興なかるべし。人に本意なく思はせて我が心をなぐさまん事、徳に背けり。睦じき中にたはぶるゝも、人にはかりあざむきて、己が智のまさりたる事を興とす。是又禮にあらず。されば、はじめ興宴よりおこりて、ながき恨を結ぶたぐひ多し。これみな、あらそひを好む失なり。人に勝らん事を思はば、たゞ學問して、其の智を人にまさらんと思ふべし。道を學ぶとならば、善に伐らず、ともがらに爭ふべからずといふ事を知るべき故なり。大きなる職をも辭し、利をも捨つるは、たゞ學問の力なり。
第百三十一段
貧しき物は財をもて禮とし、老いたる者は力をもて禮とす。己が分をしりて、及ばざる時は、速にやむを智といふべし。許さざらんは人の誤なり。分を知らずして、強ひて勵むは己が誤なり。貧しくて分を知らざれば盗み、力衰へて分を知らざれば病をうく。
第百三十二段
鳥羽の作道は、鳥羽殿建てられて後の號にあらず。昔よりの名なり。元良親王、元日の奏賀の聲甚だ殊勝にして、大極殿より鳥羽の作道まで聞えける由、李部王の記に侍るとかや。
第百三十三段
夜の御殿は東御枕なり。おほかた、東を枕として陽氣を受くべき故に、孔子も東首し給へり。寢殿のしつらひ、或は南枕、常の事なり。白河院は、北首に御寢なりけり。「北は忌む事なり。又、伊勢は南なり。大神宮の御方を御跡にせさせ給ふ事、いかゞ」と、人申しけり。但し大神宮の遙拜は、巽に向かはせ給ふ。南にはあらず。
第百三十四段 高倉院の法華堂の三昧僧、なにがしの律師とかやいふもの、或時、鏡をとりて顏をつく/\と見て、我がかたちの見にくゝ、あさましき事をあまりに心うく覺えて、鏡さへ疎ましき心地しければ、其の後ながく鏡を恐れて手にだにとらず、更に人に交る事なし。御堂のつとめばかりにあひて、籠り居たりと聞き侍りしこそ、有りがたく覺えしか。賢げなる人も、人のうへをのみはかりて、己をば知らざるなり。我を知らずして外を知るといふ理あるべからず。されば己を知るを、物知れる人といふべし。かたち醜けれども知らず、心のおろかなるをも知らず、藝の拙きをも知らず、身の數ならぬをも知らず、年の老いぬるをも知らず、病のおかすをも知らず、死の近き事をも知らず、行ふ道の至らざるをも知らず、身の上の非を知らねば、まして外のそしりを知らず。但しかたちは鏡に見ゆ、年は數へて知る。我が身の事知らぬにはあらねど、すべきかたのなければ、知らぬに似たりとぞいはまし。かたちをあらため、齡を若くせよとにはあらず。拙きを知らば、何ぞやがて退かざる。老いぬと知らば、何ぞ閑かに身をやすくせざる。行おろかなりと知らば、何ぞ茲を思ふこと茲にあらざる。すべて、人に愛樂せられずして衆に交るは恥なり。かたち見にくゝ心おくれにして出で仕へ、無智にして大才に交り、不堪の藝をもちて堪能の座に列なり、雪のかしらをいたゞきて盛りなる人にならび、況んや及ばざる事を望み、かなはぬ事を憂へ、來らざることを待ち、人におそれ人に媚ぶるは、人の與ふる恥にあらず、貪る心にひかれて、自ら身をはづかしむるなり。貪る事のやまざるは、命を終ふる大事、今こゝに來れりと、たしかに知らざればなり。
第百三十五段
資季大納言入道とかや聞えける人、具氏宰相中將に逢ひて、「わぬしの問はれんほどのこと、何事なりとも答へ申さざらんや」といはれければ、具氏、「いかゞ侍らん」と申されけるを、「さらばあらがひ給へ」といはれて、「はか/\しき事は、かたはしも學び知り侍らねば、尋ね申すまでもなし。何となきそゞろごとの中に、おぼつかなき事をこそ問ひ奉らめ」と申されけり。「ましてこゝもとのあさき事は、何事なりとも明らめ申さん」といはれければ、近習の人々、女房なども、「興あるあらがひなり。おなじくは、御前にて爭はるべし。負けたらん人は、供御をまうけらるべし」と定めて、御前にてめし合はせられたりけるに、具氏、「幼くより聞きならひ侍れど、其の心知らぬこと侍り。『むまのきつりやう、きつにのをか、なかくぼれいりくれんどう』と申す事は、如何なる心にか侍らん、承らん」と申されけるに、大納言入道はたとつまりて、「是はそゞろごとなれば、いふにも足らず」といはれけるを、「もとより深き道は知り侍らず。そゞろごとを尋ね奉らんと定め申しつ」と申されければ、大納言入道、負になりて、所課いかめしくせられたりけるとぞ。
第百三十六段
醫師あつしげ、故法皇の御前にさぶらひて、供御の參りけるに、「今參り侍る供御の色々を、文字も功能も尋ね下されて、そらに申し侍らば、本草に御覧じあはせられ侍れかし。一つも申し誤り侍らじ」と申しける時しも、六條故内府參り給ひて、「有房ついでに物ならひ侍らん」とて、「まづしほといふ文字は、いづれの偏にか侍らん」と問はれたりけるに、「土偏に候」と申したりければ、「才のほど既にあらはれにたり。いまはさばかりにて候へ。ゆかしきところなし」と申されけるに、とよみになりて、まかり出でにけり。
下 花は盛りに
第百三十七段
花は盛りに、月はくまなきをのみ見るものかは。雨にむかひて月をこひ、たれこめて春の行衞知らぬも、なほあはれに情深し。咲きぬべきほどの梢、散りしをれたる庭などこそ見所多けれ。歌の言葉がきにも、「花見にまかれりけるに、はやく散り過ぎにければ」とも、「さはる事有りてまからで」なども書けるは、「花を見て」といへるに劣れる事かは。花の散り、月の傾くをしたふ習はさる事なれど、ことにかたくななる人ぞ、「此の枝かの枝散りにけり。今は見所なし」などはいふめる。萬の事も、始終こそをかしけれ。男女の情も、ひとへに逢ひ見るをばいふものかは。逢はでやみにし憂さを思ひ、あだなる契をかこち、長き夜をひとり明かし、遠き雲井をおもひやり、淺茅が宿に昔を忍ぶこそ、色好むとは言はめ。望月のくまなきを千里の外まで眺めたるよりも、曉ちかくなりて待ち出でたるが、いと心ぶかう、青みたるやうにて、深き山の杉の梢にみえたる木の間の影、うちしぐれたるむら雲がくれのほど、またなくあはれなり。椎柴、しらがしなどのぬれたるやうなる葉の上にきらめきたるこそ、身にしみて、心あらん友もがなと、都戀しう覺ゆれ。すべて、月花をば、さのみ目にて見るものかは。春は家を立ちさらでも、月の夜は閨のうちながらも思へるこそ、いとたのもしうをかしけれ。よき人は、ひとへに好けるさまにもみえず、興ずるさまも等閑なり。かたゐなかの人こそ、色こく萬はもて興ずれ。花の本にはねぢよりたちより、あからめもせずまもりて、酒のみ連歌して、はては、おほきなる枝、心なく折り取りぬ。泉には手足さしひたして、雪にはおりたちて跡つけなど、萬の物、よそながら見る事なし。
さやうの人の祭見しさま、いとめづらかなりき。見ごといとおそし、其のほどは棧敷不用なりとて、奥なる屋にて、酒飲み物食ひ、圍棊、雙六などあそびて、棧敷には人をおきたれば、「わたりさふらふ」といふ時に、各肝つぶるゝやうに爭ひ走りのぼりて、落ちぬべきまで簾はり出でて、押し合ひつゝ、一事も見もらさじとまぼりて、とありかゝりと物毎にいひて、わたり過ぎぬれば、「又わたらんまで」といひておりぬ。たゞ物をのみ見んとするなるべし。都の人のゆゝしげなるは、睡りていとも見ず。若くすゑ/\なるは、宮仕へに立ちゐ、人の後にさぶらふは、樣惡しくもおよびかゝらず。わりなく見んとする人もなし。
何となく葵かけわたしてなまめかしきに、明けはなれぬほど、忍びて寄する車どものゆかしきを、それか、かれかなど思ひよすれば、牛飼、下部などの見知れるもあり。をかしくも、きら/\しくも、さま/\に行きかふ。見るもつれ/\ならず。暮るゝほどには、たてならべつる車ども、所なくなみゐつる人も、いづかたへかゆきつらん、程なく稀になりて、車どものらうがはしさもすみぬれば、簾、たゝみも取り拂ひ、目の前に淋しげになりゆくこそ、世のためしも思ひ知られてあはれなれ。大路見たるこそ、祭見たるにてはあれ。彼の棧敷の前をこゝら行きかふ人の、見知れるがあまた有るにて知りぬ、世の人數も、さのみは多からぬにこそ。此の人皆失せなん後、我が身死ぬべきに定まりたりとも、ほどなく待ちつけぬべし。大きなる器に水を入れて、ほそき穴をあけたらんに、したゝる事少しといふとも、怠る間なくもりゆかば、やがて盡きぬべし。都の中に多き人、死なざる日はあるべからず。一日に一人二人のみならんや。鳥部野、舟岡、さらぬ野山にも、送る數多かる日はあれど、送らぬ日はなし。されば棺をひさぐ者、作りてうち置くほどなし。若きにもよらず、強きにもよらず、思ひかけぬは死期なり。けふまで逃れ來にけるは、有り難き不思議なり。しばしも世をのどかには思ひなんや。まゝこだてといふものを雙六の石にて作りて、たて竝べたるほどは、とられん事、いづれの石とも知らねども、數へあてて一つを取りぬれば、其の外は逃れぬと見れど、又々數ふれば、彼是まぬき行くほどに、いづれも逃れざるに似たり。兵の軍に出づるは、死に近きことを知りて、家をも忘れ、身をも忘る。世を背ける草の庵には、閑かに水石をもてあそびて、これを餘所に聞くと思へるはいとはかなし。しづかなる山の奥、無常のかたき、競ひ來らざらんや。其の死に臨める事、軍の陣にすゝめるにおなじ。
第百三十八段
祭過ぎぬれば、後の葵不用なりとて、或人の、御簾なるを皆とらせられ侍りしが、色もなく覺え侍りしを、よき人のし給ふ事なれば、さるべきにやと思ひしかど、周防内侍が、かくれどもかひなきものはもろともにみすの葵の枯葉なりけりと詠めるも、母屋の御簾に葵のかゝりたる枯葉を詠めるよし、家の集に書けり。古き歌の詞書に、「枯れたる葵にさして遣はしける」とも侍り。枕草子にも、「來しかた戀しき物、枯れたる葵」と書けるこそ、いみじくなつかしう思ひよりたれ。鴨長明が四季の物語にも、「玉だれに後の葵はとまりけり」とぞ書ける。おのれとかるゝだにこそあるを、名殘なく、いかゞとり捨つべき。御帳にかゝれる藥玉も、九月九日、菊に取り代へらるゝといへば、菖蒲は菊の折までも有るべきにこそ。枇杷皇太后宮かくれ給ひて後、古き御帳の内に、菖蒲、藥玉などの枯れたるが侍りけるを見て、「をりならぬねをなほぞかけつる」と辨の乳母のいへる返事に、「あやめの草はありながら」とも、江侍從が詠みしぞかし。
第百三十九段
家に有りたき木は、松、櫻。松は五葉もよし。花は一重なるよし。八重櫻は奈良の都にのみありけるを、此の比ぞ、世に多くなり侍るなる。吉野の花、左近の櫻、皆一重にてこそあれ。八重櫻は異樣の物なり。いとこちたくねぢけたり。植ゑずともありなん。遲ざくら、又すさまじ。蟲の付きたるもむつかし。梅は白き、薄紅梅。一重なるが疾く咲きたるも、重なりたる紅梅のにほひめでたきも、皆をかし。遲き梅は、櫻に咲きあひて、覺え劣り、けおされて、枝にしぼみつきたる、心憂し。「一重なるが、まづ咲きて散りたるは、心疾く、をかし」とて、京極入道中納言は、なほ一重梅をなん軒近く植ゑられたりける。京極の屋の南むきに、今も二本侍るめり。柳、又をかし。卯月ばかりの若楓、すべて萬の花紅葉にもまさりてめでたきものなり。橘、桂、いづれも木は物古り、大きなるよし。
草は山吹、藤、杜若、撫子。池には蓮。秋の草は、荻、薄、桔梗、萩、女郎花、藤袴、紫苑、吾亦香、刈萱、龍膽、菊、黄菊も。蔦、葛、朝顏、いづれもいとたかゝらず、さゝやかなる牆に、繁からぬよし。此の外の世に稀なる物、唐めきたる名の聞きにくゝ、花も見なれぬなど、いとなつかしからず。大方、何も珍しく有り難き物は、よからぬ人のもて興ずるものなり。さやうのものなくてありなん。
第百四十段
身死して財殘る事は、智者のせざる所なり。よからぬ物貯へ置きたるも拙く、よき物は、心を留めけんとはかなし。こちたく多かる、まして口惜し。「我こそ得め」などいふものども有りて、跡に爭ひたる、樣あし。後は誰にと心ざす物あらば、生けらんうちにぞ讓るべき。朝夕なくてかなはざらん物こそあらめ、其の外は何ももたでぞあらまほしき。
第百四十一段
悲田院の堯蓮上人は、俗姓は三浦のなにがしとかや、雙なき武者なり。故郷の人の來りて物語すとて、「吾妻人こそ、いひつる事は頼まるれ。都の人は、ことうけのみよくて、實なし」といひしを、聖、「それはさこそおぼすらめども、己は都に久しく住みて、なれて見侍るに、人の心劣れりとは思ひ侍らず。なべて心やはらかに情ある故に、人のいふほどの事、けやけく否びがたくて、萬え言ひ放たず、心弱くことうけしつ。僞せんとは思はねど、乏しくかなはぬ人のみあれば、おのづから本意とほらぬ事多かるべし。吾妻人は、我がかたなれど、げには心の色なく情おくれ、ひとへにすぐよかなるものなれば、はじめより否といひて止みぬ。にぎはひ豊なれば、人にはたのまるるぞかし」とことわられ侍りしこそ、この聖、聲うちゆがみ、あら/\しくて、聖教のこまやかなる理、いとわきまへずもやと思ひしに、此の一言の後、心にくゝなりて、多かる中に寺をも住持せらるゝは、かくやはらぎたる所有りて、其の益もあるにこそと覺え侍りし。
第百四十二段
心なしと見ゆる者も、よき一言はいふものなり。ある荒夷の恐しげなるが、かたへにあひて「御子はおはすや」と問ひしに、「ひとりももち侍らず」と答へしかば、「さては、物のあはれはしり給はじ。情なき御心にぞものし給ふらんと、いとおそろし。子故にこそ、萬のあはれは思ひ知らるれ」といひたりし、さもありぬべき事なり。恩愛の道ならでは、かゝるものの心に慈悲ありなんや。孝養の心なき者も、子持ちてこそ親の志はおもひ知るなれ。世を捨てたる人の、萬にするすみなるが、なべてほだし多かる人の、萬にへつらひ、望深きを見て、無下に思ひ腐すは僻事なり。其の人の心になりて思へば、誠に悲しからん親のため、妻子のためには、恥をも忘れ、盗みもしつべき事なり。されば、盗人をいましめ、僻事をのみ罪せんよりは、世の人の饑ゑず寒からぬやうに、世をば行はまほしきなり。人恒の産なき時は恒の心なし。人きはまりて盗みす。世をさまらずして凍餒の苦しみあらば、とがの者絶ゆべからず。人を苦しめ法をおかさしめて、それを罪なはん事、不便のわざなり。さて、いかゞして人を惠むべきとならば、上のおごり費す所をやめ、民を撫で、農をすゝめば、下に利あらん事疑ひ有るべからず。衣食尋常なるうへに僻事せん人をぞ、まことの盗人とはいふべき。
第百四十三段
人の終焉の有樣のいみじかりし事など、人の語るを聞くに、たゞ、閑かにしてみだれずと言はば、心にくかるべきを、おろかなる人は、あやしく異なる相を語りつけ、いひし言葉も、振舞も、己が好む方にほめなすこそ、其の人の日來の本意にもあらずやと覺ゆれ。此の大事は、權化の人も定むべからず。博學の士もはかるべからず。己違ふ所なくば、人の見聞くにはよるべからず。
第百四十四段
栂尾の上人、道を過ぎ給ひけるに、河にて馬洗ふ男、「あし/\」といひければ、上人立ちどまりて、「あなたふとや。宿執開發の人かな。阿字々々と唱ふるぞや。如何なる人の御馬ぞ、あまりにたふとく覺ゆるは」と、尋ね給ひければ、「府生殿の御馬に候」と答へけり。「こはめでたき事かな。阿字本不生にこそあなれ。嬉しき結縁をもしつるかな」とて、感涙をのごはれけるとぞ。
第百四十五段
御隨身秦重躬、北面の下野入道信願を、「落馬の相ある人なり、よく/\つゝしみ給へ」といひけるを、いと眞しからず思ひけるに、信願馬より落ちて死ににけり。道に長じぬる一言、神のごとしと人思へり。さて、「いかなる相ぞ」と人の問ひければ、「きはめて桃尻にして、沛艾の馬を好みしかば、此の相をおほせ侍りき。いつかは申し誤りたる」とぞ云ひける。
第百四十六段
明雲座主、相者に逢ひ給ひて、「己若し兵仗の難やある」と尋ね給ひければ、相人、「誠に其の相おはします」と申す。「いかなる相ぞ」と尋ね給ひければ、「傷害のおそれおはすまじき御身にて、かりにもかくおぼしよりて尋ね給ふ、是れ既に其のあやぶみのきざしなり」と申しけり。果して矢に當りて失せ給ひにけり。
第百四十七段
灸治あまた所になりぬれば、神事にけがれありといふ事、ちかく人のいひ出せるなり。格式等にもみえずとぞ。
第百四十八段
四十以後の人、身に灸を加へて三里をやかざれば、上氣の事あり。必ず灸すべし。
第百四十九段
鹿茸を鼻にあてて嗅ぐべからず、小さき蟲有りて、鼻より入りて腦を食むといへり。
第百五十段
能をつかんとする人、よくせざらんほどは、なまじひに人に知られじ。うち/\よく習ひえてさし出でたらんこそ、いと心にくからめと、常に言ふめれど、かくいふ人、一藝も習ひ得ることなし。いまだ堅固かたほなるより、上手の中にまじりて、毀り笑はるゝにも恥ぢず、つれなく過ぎて嗜む人、天性其の骨なけれども、道になづまず、みだりにせずして年を送れば、堪能の嗜まざるよりは、終に上手の位に至り、徳たけ、人に許されて、雙なき名を得る事なり。天下の物の上手といへども、始は不堪のきこえもあり、無下の瑕瑾もありき。されども其の人、道のおきて正しく、是を重くして放埒せざれば、世の博士にて、萬人の師となる事、諸道かはるべからず。
第百五十一段
或人の云はく、年五十になるまで上手に至らざらん藝をば捨つべきなり。勵み習ふべき行末もなし。老人の事をば、人もえ笑はず。衆に交りたるも、あいなく見苦し。大方萬のしわざは止めて、暇あるこそ、めやすくあらまほしけれ。世俗の事に携はりて生涯を暮すは、下愚の人なり。ゆかしく覺えん事は、學び聞くとも、其の趣を知りなば、覺束なからずしてやむべし。もとより望むことなくして止まんは、第一の事なり。
第百五十二段
西大寺靜然上人、腰かゞまり、眉白く、誠に徳たけたる有樣にて、内裏へ參られたりけるを、西園寺内大臣殿、「あな、尊とのけしきや」とて、信仰のきそくありければ、資朝卿是を見て、「年の寄りたるに候」と申されけり。後日に、むく犬のあさましく老いさらぼひて、毛はげたるをひかせて、「此の氣色尊く見えて候」とて、内府へ參らせられたりけるとぞ。
第百五十三段
爲兼大納言入道召捕られて、武士どもうち圍みて、六波羅へ率て行きければ、資朝卿、一條わたりにてこれを見て、「あなうらやまし。世にあらん思出、かくこそあらまほしけれ」とぞ言はれける。
第百五十四段
此の人、東寺の門に雨宿りせられたりけるに、不具者共の集りゐたるが、手も足もねぢゆがみ、うちかへりて、いづくも不具に異樣なるを見て、とり/\に類なき曲者なり、尤も愛するに足れりと思ひて、まもり給ひけるほどに、やがて其の興盡きて、見にくゝいぶせく覺えければ、たゞすなほに珍しからぬ物にはしかずと思ひて、歸りて後、此の間植木を好み、異樣に曲折あるを求めて目を喜ばしめつるは、彼のかたはを愛するなりけりと、興なく覺えければ、鉢に植ゑられける木ども、皆掘り捨てられにけり。さも有りぬべき事なり。
第百五十五段
世にしたがはん人は、先づ機嫌を知るべし。ついで惡しき事は、人の耳にもさかひ、心にも違ひて、其の事成らず。さやうの折節を心得べきなり。但し、病を受け、子産み、死ぬる事のみ、機嫌をはからず。ついであしとて、やむことなし。生住異滅の移り變る實の大事は、たけき河の漲り流るゝが如し。しばしも滯らず、たゞちにおこなひゆくものなり。されば眞俗につけて、必ず果し遂げんと思はん事は、機嫌をいふべからず。とかくのもよひなく、足をふみとゞむまじきなり。春暮れて後、夏になり、夏はてて秋の來るにはあらず。春はやがて夏の氣をもよほし、夏より既に秋はかよひ、秋は則ち寒くなり、十月は小春の天氣、草も青くなり、梅もつぼみぬ。木の葉の落つるも、まづ落ちてめぐむにはあらず、下よりきざしつはるに堪へずして、落つるなり。迎ふる氣、下にまうけたる故に、待ち取るついで、甚だ速し。生老病死の移り來る事、又是に過ぎたり。四季はなほ定まれるついであり。死期はついでを待たず。死は前よりしも來らず。かねて後に迫れり。人皆死ある事を知りて、待つことしかも急ならざるに、覺えずして來る。沖の干瀉遙なれども、磯より潮の滿つるが如し。
第百五十六段
大臣の大饗は、さるべき所を申しうけて行ふ、常の事なり。宇治左大臣殿は、東三條殿にて行はる。内裏にてありけるを、申されけるによりて、他所へ行幸ありけり。させることのよせなけれども、女院の御所など借り申す、故實なりとぞ。
第百五十七段
筆を取れば物書かれ、樂器をとれば音をたてんと思ふ。盃をとれば酒を思ひ、骰子を取れば攤うたんことを思ふ。心は必ず事に觸れて來る。かりにも不善の戲れをなすべからず。
あからさまに聖教の一句を見れば、何となく前後の文も見ゆ。率爾にして多年の非を改むる事もあり。かりに今此の文をひろげざらましかば、此の事を知らんや。是れ即ち觸るゝ所の益なり。心更に起らずとも、佛前にありて數珠をとり經をとらば、怠るうちにも善業おのづから修せられ、散亂の心ながらも繩床に坐せば、覺えずして禪定なるべし。事理もとより二つならず。外相若しそむかざれば、内證必ず熟す。しひて不信を云ふべからず。仰ぎて是を尊むべし。
第百五十八段
「盃の底を捨つる事はいかゞ心得たる」と、或人の尋ねさせ給ひしに、「凝當と申し侍るは、底に凝りたるを捨つるにや候らん」と申し侍りしかば、「さにはあらず。魚道なり。流を殘して、口のつきたる所をすゝぐなり」とぞおほせられし。
第百五十九段
「みなむすびといふは、絲を結び重ねたるが、蜷といふ貝に似たればいふ」と、或やん事なき人仰せられき。になといふは誤なり。
第百六十段
門に額懸くるを「うつ」といふはよからぬにや。勘解由小路二品禪門は、「額懸くる」
とのたまひき。「見物の棧敷うつ」もよからぬにや。「ひらばりうつ」などは常の事なり。「棧敷かまふる」などいふべし。「護摩たく」といふもわろし。「修する」「護摩する」など云ふなり。「行法も、法の字を澄みていふ、わろし。濁りていふ」と、清閑寺僧正仰せられき。常にいふ事に、かゝる事のみ多し。
第百六十一段
花のさかりは、冬至より百五十日とも、時正の後七日ともいへど、立春より七十五日、大樣違はず。
第百六十二段
遍照寺の承仕法師、池の鳥を日來飼ひつけて、堂の内まで餌をまきて、戸一つ開たれば、數も知らず入り籠りける後、己も入りて、たてこめて、捕へつゝ殺しけるよそほひ、おどろ/\しく聞えけるを、草刈る童聞きて、人に告げければ、村の男共おこりて入りて見るに、大雁どもふためきあへる中に、法師まじりて、打ち伏せ、ねぢ殺しければ、この法師を捕へて、所より使廳へ出したりけり。殺す所の鳥を頸に掛けさせて、禁獄せられにけり。基俊大納言、別當の時になん侍りける。
第百六十三段
太衝の太の字、點うつ、うたずといふ事、陰陽のともがら、相論の事有りけり。もりちか入道申し侍りしは、「吉平が自筆の占文の裏に書かれたる御記、近衞の關白殿にあり。點うちたるを書きたり」と申しき。
第百六十四段
世の人相會ふ時、暫くも黙止する事なし。必ず言葉あり。其の事を聞くに、多くは無益の談なり。世間の浮説、人の是非、自他のために失多く得少し。これを語る時、互の心に無益の事なりといふ事を知らず。
第百六十五段
東の人の都の人に交り、都の人の東に行きて身をたて、又本寺本山を離れぬる顯密の僧、すべて我が俗に非ずして人に交れる、見苦し。
第百六十六段
人間の營みあへる業を見るに、春の日に雪佛を作りて、其のために金銀珠玉の飾を營み、堂を建てんとするに似たり。其のかまへを待ちて、よく安置してんや。人の命ありと見る程も、下より消ゆること雪の如くなるうちに、營みまつ事甚だ多し。
第百六十七段
一道に携はる人、あらぬ道のむしろにのぞみて、「あはれ我が道ならましかば、かくよそに見侍らじものを」といひ、心にも思へる事、常のことなれど、よにわろく覺ゆるなり。知らぬ道の羨ましく覺えば、「あなうらやまし。などかならはざりけん」といひてありなん。我が智をとり出でて人に爭ふは、角あるものの角をかたぶけ、牙あるものの牙をかみ出だす類なり。
人としては、善に誇らず、物と爭はざるを徳とす。他に勝ることのあるは、大きなる失なり。品の高さにても、才藝の勝れたるにても、先祖の譽にても、人に勝れりと思へる人は、たとひ言葉に出でてこそ言はねども、内心にそこばくのとがあり。つゝしみて是を忘るべし。をこにも見え、人にもいひ消たれ、禍をも招くはたゞこの慢心なり。一道にも誠に長じぬる人は、みづから明かに其の非を知る故に、志常に滿たずして、終に物に伐る事なし。
第百六十八段
年老いたる人の、一事すぐれたる才の有りて、「此の人の後には誰にか問はん」などいはるゝは、老のかたうどにて、生けるも徒らならず。さはあれど、それもすたれたる所のなきは、一生此の事にて暮れにけりと、拙く見ゆ。「今は忘れにけり」といひてありなん。大方は知りたりとも、すゞろに言ひちらすはさばかりの才にはあらぬにやと聞え、おのづから誤もありぬべし。「さだかにも辨へ知らず」などいひたるは、なほまことに道のあるじとも覺えぬべし。まして、知らぬ事、したり顏に、おとなしくもどきぬべくもあらぬ人のいひきかするを、さもあらずと思ひながら聞き居たる、いとわびし。
第百六十九段
「何事の式といふ事は、後嵯峨の御代までは云はざりけるを、近きほどよりいふ詞なり」と、人の申し侍りしに、建禮門院の右京大夫、後鳥羽院の御位ののち、又うちずみしたる事をいふに、「世のしきも變りたる事はなきにも」と書きたり。
第百七十段
さしたる事なくて人のがり行くは、よからぬ事なり。用有りて行きたりとも、其の事果てなば、とく歸るべし。久しく居たる、いとむづかし。人とむかひたれば、詞多く、身も草臥れ、心も閑かならず、萬の事さはりて時をうつす。互のため益なし。いとはしげにいはんもわろし。心づきなき事あらん折は、なか/\その由をもいひてん。同じ心にむかはまほしく思はん人の、つれ/\にて、「いましばし。今日は、心閑かに」などいはんは、此の限にはあらざるべし。阮籍が青き眼、誰も有るべきことなり。其のこととなきに人の來りて、長閑に物語りして歸りぬる、いとよし。又文も、「久しくきこえさせねば」などばかりいひおこせたる、いとうれし。
第百七十一段
貝をおほふ人の、我が前なるをばおきて、よそを見渡して、人の袖のかげ、膝の下まで目をくばる間に、前なるをば人におほはれぬ。よくおほふ人は、餘所までわりなく取るとはみえずして、近きばかりおほふやうなれど、おほくおほふなり。棊盤の隅に、石をたててはじくに、むかひなる石をまぼりてはじくは當らず。我が手許をよく見て、こゝなるひじりめをすぐにはじけば、たてたる石必ず當る。萬の事、外にむきて求むべからず。たゞこゝもとを正しくすべし。清獻公が言葉に、「好事を行じて前程を問ふことなかれ」といへり。世をたもたん道も、かくや侍らん。内をつゝしまず、輕くほしきまゝにしてみだりなれば、遠國必ずそむく時、はじめてはかりごとを求む。「風にあたり、濕にふして、病を神靈に訴ふるはおろかなる人なり」と醫書に言へるが如し。目の前なる人の愁をやめ、惠をほどこし、道を正しくせば、其の化遠く流れん事を知らざるなり。禹のゆきて三苗を征せしも、師を班して徳を敷くにはしかざりき。
第百七十二段
若き時は、血氣うちに餘り、心物に動きて情欲多し。身を危ぶめてくだけやすき事、珠を走らしむるに似たり。美麗を好みて寶を費し、是を捨てて苔の袂にやつれ、勇める心さかりにして物と爭ひ、心に恥ぢ羨み、好む所日々に定らず。色にふけり情にめで、行をいさぎよくして百年の身を誤り、命を失へるためし願はしくして、身の全く久しからん事をば思はず。好ける方に心ひきて、ながき世がたりともなる。身をあやまつ事は、若きときのしわざなり。老いぬる人は、精神衰へ、淡くおろそかにして、感じ動く所なし。心おのづから靜かなれば、無益のわざをなさず。身をたすけて愁なく、人のわづらひなからん事を思ふ。老いて智の若き時に勝れる事、若くしてかたちの老いたるにまされるが如し。
第百七十三段
小野小町が事、きはめて定かならず。衰へたるさまは、玉造と云ふ文に見えたり。此の文、清行が書けりといふ説あれど、高野大師の御作の目録にいれり。大師は承和のはじめにかくれ給へり。小町がさかりなる事、其の後の事にや。なほ覺束なし。
第百七十四段
小鷹によき犬、大鷹に使ひぬれば、小鷹にわろくなるといふ。大につき小をすつることわり、誠にしかなり。人事多かる中に、道を樂しぶより氣味深きはなし。是れ實の大事なり。一度道を聞きてこれに志さん人、いづれのわざかすたれざらん。何事をか營まん。おろかなる人といふとも、賢き犬の心に劣らんや。
第百七十五段
世には心えぬ事の多きなり。ともある毎にはまづ酒をすゝめて、強ひ飲ませたるを興とする事、如何なる故とも心えず。飲む人の顏いと堪へ難げに眉をひそめ、人目をはかりて捨てんとし、逃げんとするを、捕へて引きとゞめて、すゞろに飲ませつれば、うるはしき人も忽に狂人となりてをこがましく、息災なる人も目の前に大事の病者となりて、前後も知らず倒れ伏す。祝ふべき日などは、あさましかりぬべし。明くる日まで頭いたく、物食はず、によびふし、生をへだてたるやうにして昨日の事覺えず。公私の大事を缺きて、わづらひとなる。人をしてかゝるめを見する事、慈悲もなく、禮儀にもそむけり。かく辛きめにあひたらん人、ねたく口をしと思はざらんや。人の國にかゝる習ひあなりと、これらになき人事にて傳へ聞きたらんは、あやしく不思議に覺えぬべし。人の上にて見たるだに心憂し。思ひ入りたるさまに心にくしと見し人も、思ふ所なく笑ひのゝしり、詞多く、烏帽子ゆがみ、紐はづし、脛高くかゝげて、用意なき氣色、日來の人とも覺えず。女は、額髪はれらかに掻きやり、まばゆからず顏うちさゝげてうち笑ひ、盃持てる手にとりつき、よからぬ人は、さかなとりて口にさしあて、自らも食ひたる、樣あし。聲の限り出して、各うたひ舞ひ、年老いたる法師召出されて、黒く汚き身をかたぬぎて、目もあてられずすぢりたるを、興じ見る人さへうとましく憎し。或は又、我が身いみじき事どもかたはらいたく云ひきかせ、或は醉ひ泣きし、下ざまの人は、のりあひいさかひて、あさましく恐ろし。恥ぢがましく心憂き事のみ有りて、果は許さぬ物どもおしとりて、縁より落ち、馬車より落ちてあやまちしつ。物にも乘らぬきはは、大路をよろぼひ行きて、築泥、門の下などにむきて、えもいはぬ事どもしちらし、年老い袈裟かけたる法師の、小わらはの肩をおさへて聞えぬ事どもいひつゝよろめきたる、いとかはゆし。かゝる事をしても、此の世も後の世も益有るべきわざならば、いかゞはせん。此の世にはあやまち多く、財を失ひ、病をまうく。百藥の長とはいへど、萬の病は酒よりこそ起れ。憂忘るといへど、醉ひたる人ぞ、過ぎにし憂さをも思ひ出でて泣くめる。後の世は人の智慧を失ひ、善根をやくこと火の如くして、惡をまし、萬の戒を破りて地獄に落つべし。「酒をとりて人に飲ませたる人、五百生が間、手無き者に生まる」とこそ、佛は説き給ふなれ。かくうとましと思ふ物なれど、おのづから捨てがたき折も有るべし。月の夜、雪の朝、花の本にても、心長閑に物語して盃出したる、萬の興を添ふるわざなり。つれづれなる日、思ひの外に友の入り來て、とりおこなひたるも心なぐさむ。なれ/\しからぬあたりの御簾の中より、御くだ物、みきなど、よきやうなる氣はひしてさし出されたる、いとよし。冬、狹き所にて、火にて物煎りなどして、へだてなきどちさしむかひておほく飲みたる、いとをかし。旅のかり屋、野山などにて、「御さかな何がな」などいひて、芝の上にて飲みたるもをかし。いたういたむ人の、強ひられて少し飲みたるもいとよし。よき人の、とりわきて、「今ひとつ、上すくなし」などのたまはせたるもうれし。近づかまほしき人の上戸にて、ひし/\と馴れぬる、又うれし。さはいへど、上戸はをかしく罪ゆるさるゝものなり。醉ひ草臥て朝寢したる所を、あるじのひきあけたるに、惑ひて、ほれたる顏ながら、細きもとどりさし出し、物もきあへず抱き持ち、ひきしろひて逃ぐるかいとり姿のうしろ手、毛生ひたる細き脛のほど、をかしくつき/\し。
第百七十六段
黒戸は、小松御門位につかせ給ひて、昔たゞ人にておはしましし時、まさな事せさせ給ひしを忘れ給はで、常にいとなませ給ひける間なり。御薪にすゝけたれば、黒戸といふとぞ。
第百七十七段
鎌倉の中書王にて御鞠ありけるに、雨ふりて後、未だ庭の乾かざりければ、いかゞせんと沙汰有りけるに、佐々木隱岐入道、鋸の屑を車に積みて、多く奉りたりければ、一庭に敷かれて、泥土のわづらひなかりけり。とりためけん用意有り難しと、人感じあへりけり。此の事を或者の語り出でたりしに、吉田中納言の、「乾砂子の用意やはなかりける」とのたまひたりしかば、はづかしかりき。いみじと思ひける鋸の屑、賤しく異樣の事なり。庭の儀を奉行する人、乾砂子を設くるは故實なりとぞ。
第百七十八段
或所のさぶらひども、内侍所の御神樂を見て、人に語るとて、「寶劍をば其の人ぞ持ち給ひつる」などいふを聞きて、うちなる女房の中に、「別殿の行幸には、晝の御座の御劍にてこそあれ」としのびやかにいひたりし、心にくかりき。その人古き典侍なりけるとかや。
第百七十九段
入宋の沙門道眼上人、一切經を持來して、六波羅のあたり、やけ野といふ所に安置して、ことに首楞嚴經を講じて、那蘭陀寺と號す。其の聖の申されしは、「那蘭陀寺は、大門北むきなりと、江帥の説とて云ひ傳へたれど、西域傳、法顯傳などにもみえず、更に所見なし。江帥は、如何なる才學にてか申されけん、覺束なし。唐土の西明寺は、北むき勿論なり」と申しき。
第百八十段
さぎちやうは、正月に打ちたるぎちやうを、眞言院より神泉苑へ出して、燒きあぐるなり。「法成就の池にこそ」とはやすは、神泉苑の池をいふなり。
第百八十一段
「ふれ/\こゆき、たんばのこゆき」といふ事、よねつきふるひたるに似たれば、粉雪といふ。「たまれ粉雪」と云ふべきを、誤りて、「たんばの」とはいふなり。「かきや木のまたに」とうたふべしと、或物しり申しき。昔よりいひける事にや。鳥羽院をさなくおはしまして、雪のふるにかく仰せられけるよし、讃岐典侍が日記に書きたり。
第百八十二段
四條大納言隆親卿、からざけと云ふものを供御に參らせられたりけるを、「かくあやしき物、參るやうあらじ」と人の申しけるを聞きて、大納言、「鮭といふ魚參らぬ事にてあらんにこそあれ。鮭のしらぼし、なでふ事かあらん。鮎のしらぼしは參らぬかは」と申されけり。
第百八十三段
人つく牛をば角をきり、人くふ馬をば耳をきりて、そのしるしとす。しるしをつけずして人をやぶらせぬるは、ぬしのとがなり。人くふ犬をば養ひ飼ふべからず。是れ皆とがあり。律の禁なり。 第百八十四段 相模守時頼の母は、松下禪尼とぞ申しける。守をいれ申さるゝ事ありけるに、すゝけたる明り障子の破ればかりを、禪尼手づから、小刀してきりまはしつゝ張られければ、兄の城介義景、其の日のけいめいして候ひけるが、「給はりて、なにがし男に張らせ候はん。さやうの事に心得たる者に候」と申されければ、「其の男、尼が細工によもまさり侍らじ」とて、なほ一間づつ張られけるを、義景、「皆を張り替へ候はんは、はるかにたやすく候ふべし。まだらに候も見苦しくや」と、重ねて申されければ、「尼も、後はさは/\と張り替へんと思へども、今日ばかりは、わざとかくて有るべきなり。物は破れたる所ばかりを修理して用ゐる事ぞと、若き人に見習はせて、心つけんためなり」と申されける、いと有り難かりけり。世ををさむる道、儉約を本とす。女性なれども聖人の心にかよへり。天下をたもつ程の人を子にてもたれける、誠に、たゞ人にはあらざりけるとぞ。
第百八十五段
城陸奥守泰盛は、雙なき馬乘りなりけり。馬をひき出させけるに、足を揃へてしきみをゆらりと越ゆるを見ては、「是はいさめる馬なり」とて、鞍を置き換へさせけり。又、足をのべてしきみに蹴當てぬれば、「是は鈍くしてあやまち有るべし」とて、乘らざりけり。道を知らざらん人、かばかり恐れなんや。
第百八十六段
吉田と申す馬乘の申し侍りしは、「馬ごとにこはきものなり。人の力、爭ふべからずと知るべし。乘るべき馬をばまづよく見て、強き所弱き所を知るべし。次に轡、鞍の具に危き事やあると見て、心にかゝる事あらば、其の馬を走すべからず。此の用意を忘れざるを、馬乘とは申すなり。これ秘藏の事なり」と申しき。
第百八十七段 萬の道の人、たとひ不堪なりといへども、堪能の非家の人にならぶ時、必ずまさる事は、たゆみなくつゝしみて輕々しくせぬと、ひとへに自由なるとのひとしからぬなり。藝能所作のみにあらず、大方の振舞、心づかひも、おろかにしてつゝしめるは、得の本なり。たくみにしてほしきまゝなるは、失の本なり。
第百八十八段
或者、子を法師になして、「學問して因果の理をも知り、説經などして世渡るたづきともせよ」といひければ、教のまゝに説經師にならんために、先づ馬に乘り習ひけり。
輿車はもたぬ身の、導師に請ぜられん時、馬などむかへにおこせたらんに、桃尻にて落ちなんは、心憂かるべしと思ひけり。次に、佛事の後酒などすゝむる事あらんに、法師の無下に能なきは檀那すさまじく思ふべしとて、早歌と云ふことを習ひけり。二つのわざ、やう/\さかひに入りければ、いよ/\よくしたく覺えて嗜みけるほどに、説經習ふ隙なくて、年よりにけり。
此の法師のみにもあらず、世間の人、なべて此の事あり。若き程は、諸事につけて、身をたて、大きなる道をも成じ、能をもつき、學問をもせんと、行末久しくあらます事ども心にはかけながら、世を長閑に思ひて打ちおこたりつゝ、まづさしあたりたる目の前の事にのみまぎれて、月日を送れば、こと/\なす事なくして身は老いぬ。終に物の上手にもならず。思ひしやうに身をももたず、悔ゆれども取返さるゝ齡ならねば、走りて坂を下る輪の如くに衰へゆく。されば、一生のうち、むねとあらまほしからん事の中に、いづれかまさるとよく思ひくらべて、第一の事を案じ定めて、其の外は思ひ捨てて、一事を勵むべし。一日の中、一時の中にも、あまたのことの來らんなかに、少しも益のまさらん事をいとなみて、其の外をばうち捨てて、大事を急ぐべきなり。何方をも捨てじと心にとりもちては、一事も成るべからず。たとへば棊をうつ人、一手も徒らにせず、人にさきだちて、小を捨て大につくが如し。それにとりて、三つの石を捨てて十の石につくことはやすし。十を捨てて十一につくことはかたし。一つなりともまさらんかたへこそつくべきを、十までなりぬれば、惜しく覺えて、多くまさらぬ石にはかへにくし。是をも捨てず、彼をもとらんと思ふ
心に、彼をも得ず、是をも失ふべき道なり。京に住む人、急ぎて東山に用ありて、既に行きつきたりとも、西山に行きて其の益まさるべき事を思ひえたらば、門より歸りて、西山へゆくべきなり。こゝまで來著きぬれば、此の事をば先いひてん。日をさゝぬ事なれば、西山の事は、歸りて又こそ思ひたゝめと思ふ故に、一時の懈怠、即ち一生の懈怠となる。是を恐るべし。一事を必ずなさんと思はば、他の事の破るゝをもいたむべからず。人の嘲をも恥づべからず。萬事にかへずしては、一の大事成るべからず。人の數多有りける中にて、或者、「ますほのすゝき、まそほのすゝきなどいふ事あり。わたのべの聖、此の事を傳へ知りたり」と語りけるを、登蓮法師其の座に侍りけるが、聞きて、雨の降りけるに、「蓑かさやある、貸し給へ。彼の薄の事ならひに、わたのべの聖のがり尋ねまからん」といひけるを、「あまりに物騒がし。雨やみてこそ」と人のいひければ、「無下の事をも仰せらるゝものかな。人の命は雨の晴間をも待つものかは。我も死に、聖も失せなば、尋ね聞きてんや」とて、走り出でて行きつゝ、習ひ侍りにけりと申し傳へたるこそ、ゆゝしく有り難う覺ゆれ。「敏きときは則ち功あり」とぞ、論語と云ふ文にも侍るなる。此の薄をいぶかしく思ひけるやうに、一大事因縁をぞ思ふべかりける。
第百八十九段
今日は其の事をなさんと思へど、あらぬ急ぎ先づ出で來てまぎれ暮し、待つ人はさはり有りて、たのめぬ人は來り、たのみたる方の事は違ひて、思ひよらぬ道ばかりはかなひぬ。わづらはしかりつる事はことなくて、やすかるべき事は、いと心ぐるし。日々に過ぎ行くさま、かねて思ひつるには似ず。一年の中もかくの如し。一生の間も、又しかなり。
かねてのあらまし、皆たがひゆくかと思ふに、おのづからたがはぬ事もあれば、いよいよ物は定めがたし。不定と心得ぬるのみ、誠にてたがはず。
第百九十段
妻といふものこそ、をのこの持つまじき物なれ。「いつも獨り住みにて」など聞くこそ、心にくけれ。「誰がしが壻になりぬ」とも、又「如何なる女を取りすゑて、相住む」など聞きつれば、無下に心劣りせらるゝわざなり。異なる事なき女を、よしと思ひさだめてこそ添ひ居たらめと、賤しくもおしはかられ、よき女ならば、此の男をぞ、らうたくして、あが佛とまもりゐたらめ、たとへば、さばかりにこそと覺えぬべし。まして家のうちを行ひをさめたる女、いと口惜し。子などいできて、かしづき愛したる、心憂し。男なくなりて後、尼になりて年よりたるありさま、なき跡まであさまし。いかなる女なりとも、明暮そひ見んには、いと心づきなく、憎かりなん。女のためも半空にこそならめ。よそながら、時々通ひ住まんこそ、年月經ても絶えぬ仲らひともならめ。あからさまに來て、とまり居などせんは、めづらしかりぬべし。
第百九十一段
夜に入りて、物のはえなしといふ人、いと口惜し。萬のもののきら、かざり、色ふしも、夜のみこそめでたけれ。晝は、ことそぎおよづけたる姿にても有りなん。夜は、きらゝかに、花やかなる裝束いとよし。人のけしきも、夜のほかげぞ、よきはよく、物言ひたる聲も、暗くて聞きたる、用意ある、心にくし。にほひも、ものの音も、ただ夜ぞひときはめでたき。
さしてことなる事なき夜、うち更けて參れる人の、清げなるさましたる、いとよし。若きどち、心とゞめて見る人は、時をも分かぬものなれば、ことにうちとけぬべき折節ぞ、けはれなくひきつくろはまほしき。よき男の日暮れてゆするし、女も夜更くる程にすべりつゝ、鏡とりて、顏などつくろひて出づるこそをかしけれ。
第百九十二段
神佛にも、人の詣でぬ日、夜まゐりたる、よし。
第百九十三段
くらき人の、人をはかりて、其の智を知れりと思はん、さらにあたるべからず。拙き人の、棊うつ事ばかりにさとくたくみなるは、賢き人の、此の藝におろかなるを見て、己が智に及ばずと定めて、萬の道のたくみ、我が道を人の知らざるを見て、己すぐれたりと思はん事、大きなる誤なるべし。文字の法師、暗證の禪師、互にはかりて、己にしかずと思へる、共にあたらず。己が境界にあらざる物をば爭ふべからず、是非すべからず。
第百九十四段
達人の人を見る眼は、少しも誤る所有るべからず。例へば、或人の、世に虚言を構へ出して人をはかる事あらんに、すなほにまことと思ひて、いふまゝにはからるゝ人あり。あまりに深く信をおこして、なほわづらはしく虚言を心得そふる人あり。又何としも思はで、心をつけぬ人あり。又いさゝか覺束なくおぼえて、たのむにもあらず、たのまずもあらで、案じゐたる人あり。又まことしくは覺えねども、人のいふ事なれば、さもあらんとてやみぬる人もあり。又さま/\に推し、心得たるよしして、かしこげにうちうなづき、ほゝゑみてゐたれど、つやつや知らぬ人あり。又推し出して、あはれさるめりと思ひながら、なほあやまりもこそあれと、怪しむ人あり。又異なる樣もなかりけりと、手を打ちて笑ふ人あり。又心得たれども、知れりともいはず、覺束なからぬは、とかくの事なく、知らぬ人と同じやうにて過ぐる人あり。又此の虚言の本意をはじめより心得て、少しもあざむかず、構へ出したる人と同じ心になりて、力を合する人あり。
愚者の中の戲だに、知りたる人の前にては、此のさま/\の得たる所、詞にても顏にても、かくれなく知られぬべし。まして、明かならん人の、惑へる我等を見んこと、掌の上の物を見んが如し。但し、かやうの推しはかりにて、佛法までをなずらへ云ふべきにはあらず。
第百九十五段
或人久我繩手を通りけるに、小袖に大口著たる人、木造の地藏を田の中の水におしひたして、ねんごろに洗ひけり。心得がたく見るほどに、狩衣の男二三人出で來て、「こゝにおはしましけり」とて、此の人を具して去にけり。久我内大臣殿にてぞおはしける。尋常におはしましける時は、神妙にやん事なき人にておはしけり。
第百九十六段
東大寺の神輿、東寺の若宮より歸座の時、源氏の公卿參られけるに、此の殿大將にてさきをおはれけるを、土御門相國、「社頭にて警蹕いかゞ侍るべからん」と申されければ、「隨身のふるまひは、兵仗の家が知る事に候」とばかり答へ給ひけり。さて後に仰せられけるは、「此の相國、北山抄を見て、西宮の説をこそ知られざりけれ。眷属の惡鬼惡神恐るゝ故に、神社にて、殊にさきをおふべき理りあり」とぞおほせられける。
第百九十七段
諸寺の僧のみにもあらず、定額の女嬬といふ事、延喜式に見えたり。すべて數定りたる公人の通號にこそ。
第百九十八段
揚名介に限らず、揚名目といふものあり。政治要略にあり。
第百九十九段
横川行宣法印が申し侍りしは、「唐土は呂の國なり。律の音なし。和國は單律の國にて、呂の音なし」と申しき。
第二百段
呉竹は葉細く、河竹は葉廣し。御溝に近きは河竹、仁壽殿のかたに寄りて植ゑられたるは呉竹なり。
第二百一段
退凡下乘の卒都婆、外なるは下乘、内なるは退凡なり。
第二百二段
十月を神無月と云ひて、神事に憚るべき由は、記したる物なし。もと文も見えず。但し、當月、諸社の祭なき故に此の名あるか。此の月、萬の神達、大神宮へ集り給ふなど云ふ説あれども、其の本説なし。さる事ならば、伊勢には殊に祭月とすべきに、その例もなし。十月、諸社の行幸、其の例も多し。但し、多くは不吉の例なり。
第二百三段
勅勘の所に靫かくる作法、今は絶えて知れる人なし。主上の御惱、大方世の中の騒がしき時は、五條の天神に靫をかけらる。鞍馬にゆぎの明神といふも、靫かけられたりける神なり。看督長の負ひたる靫を、其の家にかけられぬれば、人出で入らず。此の事絶えて後、今の世には、封をつくることになりにけり。
第二百四段
犯人をしもとにてうつ時は、拷器によせてゆひつくるなり。拷器の樣も、よする作法も、今はわきまへ知れる人なしとぞ。
第二百五段
比叡山に大師勸請の起請といふ事は、慈慧僧正書き始め給ひけるなり。起請文といふ事、法曹には其の沙汰なし。古の聖代、すべて起請文につきて行はるゝ政はなきを、近代此の事流布したるなり。又法令には、水火に穢を立てず。入物には穢あるべし。
第二百六段
徳大寺右大臣殿、檢非違使の別當の時、中門にて使廳の評定行はれける程に、官人章兼が牛はなれて、廳のうちへ入りて、大理の座のはまゆかの上に登りて、にれうちかみて臥したりけり。重き怪異なりとて、牛を陰陽師の許へ遣すべき由、各申しけるを、父の相國聞き給ひて、「牛に分別なし。足あれば、いづくへか登らざらん。おう弱の官人、たまたま出仕の微牛をとらるべきやうなし」とて、牛をば主に返して、臥したりける疊をば代へられにけり。あへて凶事なかりけるとなん。「あやしみを見てあやしまざる時は、あやしみ反りて破る」といへり。
第二百七段
龜山殿建てられんとて、地をひかれけるに、大きなる蛇、數も知らずこり集りたる塚ありけり。此の所の神なりといひて、事の由を申しければ、いかゞあるべきと勅問ありけるに、「古くより此の地を占めたる物ならば、さうなく掘り捨てられ難し」と、皆人申されけるに、此の大臣一人、「王土にをらん蟲、皇居を建てられんに、何の祟をか爲すべき。鬼神はよこしまなし。とがむべからず。たゞ皆掘り捨つべし」と申されたりければ、塚をくづして、蛇をば大井河に流してけり。さらに祟なかりけり。
第二百八段
經文などの紐を結ふに、上下よりたすきにちがへて、二筋の中より、わなの頭を横さまに引き出す事は、常の事なり。さやうにしたるをば、華嚴院弘舜僧正、ときてなほさせけり。「是は、此の比やうの事なり。いとにくし。うるはしくは、たゞくるくると巻きて、上より下へ、わなの先をさしはさむべし」と申されけり。古き人にて、かやうの事知れる人になん侍りける。
第二百九段
人の田を論ずる者、訴に負けて、ねたさに、「其の田を刈りて取れ」とて、人を遣しけるに、先づ道すがらの田をさへ刈りもてゆくを、「是は論じ給ふ所にあらず。いかにかくは」といひければ、刈る者共、「其の所とても刈るべき理なけれども、僻事せんとて罷る者なれば、いづくをか刈らざらん」とぞいひける。理り、いとをかしかりけり。
第二百十段
喚子鳥は春の物なりとばかりいひて、如何なる鳥ともさだかに記せる物なし。ある眞言書の中に、喚子鳥鳴く時、招魂の法をば行ふ次第あり。これは鵺なり。萬葉集の長歌に、「霞立つながき春日の」などつゞけたり。鵺鳥も喚子鳥のことざまにかよひてきこゆ。
第二百十一段
萬の事はたのむべからず。おろかなる人は、深く物を頼む故に、恨み怒る事あり。勢ありとて頼むべからず。強きもの先づ亡ぶ。財多しとて頼むべからず、時の間に失ひやすし。才ありとて頼むべからず、孔子も時にあはず。徳ありとて頼むべからず、顏囘も不幸なりき。君の寵をも頼むべからず、誅を受くる事速なり。奴從へりとて頼むべからず、背きはしる事あり。人の志をも頼むべからず、必ず變ず。約をも頼むべからず、信ある事少し。身をも人をも頼まざれば、是なる時は喜び、非なる時は恨みず。左右ひろければさはらず、前後遠ければ塞がらず。狹き時はひしげくだく。心を用ゐる事少しきにしてきびしき時は、物にさかひ、爭ひてやぶる。ゆるくしてやはらかなる時は、一毛も損せず。人は天地の靈なり。天地は限る所なし。人の性、何ぞ異ならん。寛大にして極らざる時は、喜怒是にさはらずして、物のためにわづらはず。
第二百十二段
秋の月はかぎりなくめでたきものなり。いつとても月はかくこそあれとて、思ひ分かざらん人は、無下に心憂かるべき事なり。
第二百十三段
御前の火爐に火をおく時は、火箸してはさむ事なし。かはらけよりたゞちに移すべし。されば、轉び落ちぬやうに、心得て炭をつむべきなり。八幡の御幸に、供奉の人、淨衣を著て、手にて炭をさゝれければ、ある有職の人、「白き物を著たる日は、火箸を用ゐる、苦しからず」と申されけり。
第二百十四段
想夫戀といふ樂は、女、男を戀ふる故の名にはあらず、本は相府蓮、文字の通へるなり。晋の王儉、大臣として、家に蓮を植ゑて愛せし時の樂なり。是より大臣を蓮府といふ。廻忽も廻鶻なり。廻鶻國とて、夷のこはき國あり。其の夷、漢に伏して後に來りて、おのれが國の樂を奏せしなり。
第二百十五段
平宣時朝臣、老の後、昔語りに、「最明寺入道或宵の間によばるゝ事有りしに、『やがて』と申しながら、直垂のなくて、とかくせしほどに、又使來りて、『直垂などのさふらはぬにや。夜なれば、異樣なりとも、疾く』とありしかば、なえたる直垂、うちうちのまゝにて罷りたりしに、銚子に土器とり添へてもて出でて、『此の酒をひとりたうべんがさう/\しければ、申しつるなり。さかなこそなけれ。人はしづまりぬらん。さりぬべき物やあると、いづくまでも求め給へ』とありしかば、紙燭さして、くまぐまを求めし程に、臺所の棚に、小土器に味噌の少しつきたるを見出でて、『これぞ求めえてさふらふ』と申ししかば、『事足りなん』とて、心よく數獻に及びて、興に入られ侍りき。其の世には、かくこそ侍りしか」と申されき。
第二百十六段 最明寺入道、鶴岡の社參の次に、足利左馬入道の許へ、先づ使を遣はして、立ちいられたりけるに、あるじまうけられたりける樣、一獻にうちあはび、二獻にえび、三獻に掻餅にて止みぬ。其の座には亭主夫婦、隆辨僧正、あるじ方の人にて坐せられけり。さて、「年毎に給はる足利の染物、心許なく候」と申されければ、「用意しさふらふ」とて、色々の染物三十、前にて女房共に小袖に調ぜさせて、後につかはされけり。その時見たる人の、近くまで侍りしが語り侍りしなり。
第二百十七段 或大福長者の云はく、「人は萬をさしおきて、ひたぶるに徳をつくべきなり。貧しくては、生ける甲斐なし。富めるのみを人とす。徳をつかんと思はば、すべからくまづ其の心づかひを修行すべし。其の心と云ふは、他の事にあらず。人間常住の思に住して、かりにも無常を觀ずること勿れ。是れ第一の用心なり。次に、萬事の用をかなふべからず。人の世にある、自他につけて所願無量なり。欲に隨ひて志を遂げんと思はば、百萬の錢有りといふとも、暫くも住すべからず。所願は止む時なし。財は盡くる期あり。限りある財をもちて、限りなき願ひに隨ふ事、得べからず。所願、心にきざす事あらば、我を亡ぼすべき惡念來れりと、かたくつゝしみ恐れて、小要をもなすべからず。次に、錢を奴の如くして使ひ用ゐる物と知らば、ながく貧苦を免るべからず。
君の如く神の如く恐れ尊みて、從へ用ゐること勿れ。次に、恥に臨むといふとも、怒り恨むる事勿れ。次に、正直にして約をかたくすべし。此の義を守りて利を求めん人は、富の來る事、火の乾けるにつき、水の下れるに從ふが如くなるべし。錢つもりて盡きざる時は、宴飲聲色を事とせず、居所をかざらず、所願を成ぜざれども、心とこしなへに安く樂し」と申しき。抑々人は、所願を成ぜんがために財を求む。錢を財とする事は、願ひをかなふるが故なり。所願あれどもかなへず、錢あれども用ゐざらんは、全く貧者と同じ。何をか樂しびとせん。此のおきては、たゞ人間の望をたちて、貧を憂ふべからずときこえたり。欲を成じて樂しびとせんよりは、しかじ、財なからんには。癰疽を病む者、水に洗ひて樂しびとせんよりは、病まざらんにはしかじ。こゝに至りては、貧富分く所なし。究竟は理即に等し。大欲は無欲に似たり。
第二百十八段 狐は人に食ひつくものなり。堀川殿にて、舎人が寢たる足を狐に食はる。仁和寺にて、夜、本寺の前を通る下法師に、狐三つ飛びかゝりて食ひつきければ、刀を拔きて是を防ぐ間、狐二疋を突く。一つはつき殺しぬ。二つは逃げぬ。法師はあまた所食はれながら、ことゆゑなかりけり。
第二百十九段
四條黄門命ぜられて云はく、「龍秋は、道にとりてはやん事なき者なり。先日來りて云はく、『短慮の至り、極めて荒涼の事なれども、横笛の五の穴は、聊かいぶかしき所の侍るかと、ひそかに是を存ず。其の故は、干の穴は平調、五の穴は下無調なり。其の間に、勝絶調を隔てたり。上の穴雙調、次に鳧鐘調をおきて、夕の穴黄鐘調なり。其の次に鸞鏡調を置きて、中の穴盤渉調。中と六とのあはひに神仙調あり。かやうに間間に皆一律を盗めるに、五の穴のみ、上の間に調子をもたずして、しかも間をくばる事等しき故に、其の聲不快なり。されば此の穴を吹く時は、必ずのく。のけあへぬ時は、物にあはず。吹きうる人難し』と申しき。料簡の至り、誠に興あり。先達、後生を畏ると云ふこと、此の事なり」と侍りき。他日に景茂が申し侍りしは、「笙は、調べおほせて持ちたれば、たゞ吹くばかりなり。笛は吹きながら、息のうちにて、かつ調べもてゆく物なれば、穴毎に口傳の上に性骨を加へて心をいるゝこと、五の穴のみにかぎらず。ひとへにのくとばかりも定むべからず。惡しく吹けばいづれの穴も心よからず。上手はいづれをも吹きあはす。呂律の物にかなはざるは、人のとがなり。器の失にあらず」と申しき。
第二百二十段
「何事も邊土は賤しくかたくななれども、天王寺の舞樂のみ都に恥ぢず」といへば、天王寺の伶人の申し侍りしは、「當寺の樂はよく圖を調べ合はせて、ものの音のめでたくとゝのほり侍る事、外よりもすぐれたり。故は、太子の御時の圖、今に侍るをはかせとす。いはゆる六時堂の前の鐘なり。其の聲黄鐘調のもなかなり。寒暑に隨ひてあがりさがり有るべき故に、二月涅槃會より聖靈會までの中間を指南とす。秘藏の事なり。此の一調子をもちて、いづれの聲をもとゝのへ侍るなり」と申しき。凡そ鐘の聲は黄鐘調なるべし。是れ無常の調子、祇園精舎の無常院の聲なり。西園寺の鐘、黄鐘調に鋳らるべしとて、あまた度鋳かへられけれどもかなはざりけるを、遠國より尋ねいだされけり。淨金剛院の鐘の聲、又黄鐘調なり。
第二百二十一段
「建治、弘安の比は、祭の日の放免のつけ物に、異樣なる紺の布四五反にて馬を作りて、尾髪にはとうしみをして、蜘蛛の絲かきたる水干につけて、歌の心などいひてわたりし事、常に見及び侍りしなども、興ありてしたる心ちにてこそ侍りしか」と、老いたる道志共の、今日も語り侍るなり。此の比は、つけもの、年を送りて過差事の外になりて、萬の重き物を多くつけて、左右の袖を人に持たせて、みづからはほこをだに持たず、息づき苦しむ有樣、いと見苦し。
第二百二十二段
竹谷乘願房、東二條院へ參られたりけるに、「亡者の追善には、何事か勝利多き」と尋ねさせ給ひければ、「光明眞言、寶篋印陀羅尼」と申されたりけるを、弟子共、「いかにかくは申し給ひけるぞ。念佛に勝る事さふらまじとは、など申し給はぬぞ」と申しければ、「我が宗なればさこそ申さまほしかりつれども、正しく、稱名を追福に修して巨益あるべしと説ける經文を見及ばねば、何にみえたるぞと、重ねて問はせ給はば、いかゞ申さんと思ひて、本經のたしかなるにつきて、此の眞言陀羅尼をば申しつるなり」とぞ申されける。
第二百二十三段
たづの大臣殿は、童名たづ君なり。鶴を飼ひ給ひける故にと申すは僻事なり。
第二百二十四段
陰陽師有宗入道、鎌倉より上りて、尋ねまうで來りしが、まづさし入りて「此の庭の徒らに廣きこと、あさましく、有るべからぬ事なり。道を知る者は、植うる事をつとむ。細道一つ殘して、皆畑に作り給へ」といさめ侍りき。誠に、少しの地をも徒らにおかんことは、益なき事なり。食ふ物、藥種など植ゑおくべし。
第二百二十五段
多久助が申しけるは、通憲入道、舞の手の中に、興有る事どもを選びて、いその禪師といひける女に教へて舞はせけり。白き水干に、さうまきをさゝせ、烏帽子をひき入れたりければ、男舞とぞいひける。禪師が娘靜と云ひける、此の藝をつげり。是れ白拍子の根元なり。佛神の本縁をうたふ。其の後源光行、多くの事を作れり。後鳥羽院の御作もあり。龜菊に教へさせ給ひけるとぞ。
第二百二十六段
後鳥羽院の御時、信濃前司行長、稽古の譽ありけるが、樂府の御論議の番に召されて、七徳の舞を二つ忘れたりければ、五徳の冠者と異名をつきにけるを、心憂き事にして、學問を捨てて遁世したりけるを、慈鎭和尚、一藝ある者をば下部までも召しおきて、不便にせさせ給ひければ、此の信濃入道を扶持し給ひけり。此の行長入道、平家物語を作りて、生佛といひける盲目に教へて語らせけり。さて山門のことを、殊にゆゝしく書けり。九郎判官の事は、くはしく知りて書きのせたり。蒲冠者の事は、よく知らざりけるにや、多くの事どもをしるしもらせり。武士の事、弓馬のわざは、生佛、東國の者にて、武士に問ひ聞きて書かせけり。かの生佛が生れつきの聲を、今の琵琶法師は學びたるなり。
第二百二十七段
六時禮讃は、法然上人の弟子、安樂といひける僧、經文を集めて作りて、つとめにしけり。其の後、太秦善觀房といふ僧、ふしはかせを定めて聲明になせり。一念の念佛の最初なり。後嵯峨院の御代よりはじまれり。法事讃も、同じく善觀房はじめたるなり。
第二百二十八段
千本の釋迦念佛は、文永の比、如輪上人、是をはじめられけり。
第二百二十九段
よき細工は、少し鈍き刀を使ふといふ。妙觀が刀はいたくたゝず。
第二百三十段
五條内裏には妖物有りけり。藤大納言殿語られ侍りしは、殿上人共黒戸にて棊を打ちけるに、御簾をかゝげて見るものあり。「誰そ」と見向きたれば、狐、人のやうについゐて、さしのぞきたるを、「あれ狐よ」ととよまれて、惑ひ逃げにけり。未練の狐、化け損じけるにこそ。
第二百三十一段
そのの別當入道は、雙なき庖丁者なり。或人の許にて、いみじき鯉をいだしたりければ、皆人、別當入道の庖丁を見ばやと思へども、たやすくうち出でんもいかゞとためらひけるを、別當入道さる人にて、「此の程百日の鯉をきり侍るを、今日缺き侍るべきにあらず。まげて申し請けん」とてきられける、いみじく、つき/\しく、興ありて人ども思へりけると、或人、北山太政入道殿に語り申されたりければ、「かやうの事、己は世にうるさく覺ゆるなり。『きりぬべき人なくば、賜べ、きらん』といひたらんは、なほよかりなん。何でふ、百日の鯉をきらんぞ」とのたまひたりし、をかしく覺えしと、人の語り給ひける、いとをかし。大方、振舞ひて興あるよりも、興なくてやすらかなるが、勝りたる事なり。稀人の饗應なども、ついでをかしきやうにとりなしたるも、誠によけれども、たゞ其の事となくてとり出でたる、いとよし。人に物をとらせたるも、ついでなくて、是を奉らんと云ひたる、まことの志なり。惜しむ由して乞はれんと思ひ、勝負の負わざにことづけなどしたる、むづかし。
第二百三十二段
すべて人は、無智無能なるべきものなり。或人の子の、見ざまなど惡しからぬが、父の前にて、人と物いふとて、史書の文を引きたりし、さかしくは聞えしかども、尊者の前にては、さらずともと覺えしなり。又、或人の許にて、琵琶法師の物語をきかんとて、琵琶を召しよせたるに、柱の一つ落ちたりしかば、「作りてつけよ」と云ふに、ある男の中に、惡しからずと見ゆるが、「古きひさくの柄ありや」などいふを見れば、爪をおほしたり。琵琶などひくにこそ。盲目法師の琵琶、其の沙汰にも及ばぬことなり。道に心得たる由にやと、かたはらいたかりき。「ひさくの柄は、ひもの木とかやいひて、よからぬ物に」とぞ、或人仰せられし。若き人は、少しの事も、よく見え、わろく見ゆるなり。
第二百三十三段
萬のとがあらじと思はば、何事にもまことありて、人を分かずうや/\しく、言葉少なからんにはしかじ。男女、老少、皆さる人こそよけれども、ことに若くかたちよき人の、ことうるはしきは、忘れがたく、思ひつかるゝものなり。萬のとがは、馴れたるさまに上手めき、所えたるけしきして、人をないがしろにするにあり。
第二百三十四段 人の物を問ひたるに、知らずしもあらじ、ありのまゝにいはんはをこがましとにや、心惑はすやうに返事したる、よからぬ事なり。知りたる事も、なほさだかにと思ひてや問ふらん。又、まことに知らぬ人もなどかなからん。うらゝかにいひきかせたらんは、おとなしく聞えなまし。人は未だ聞き及ばぬ事を、我が知りたるまゝに、「さても其の人の事のあさましさ」などばかり言ひやりたれば、「如何なる事のあるにか」と、おし返し問ひにやるこそ、心づきなけれ。世に古りぬる事をも、おのづから聞きもらすあたりもあれば、覺束なからぬやうに告げやりたらん、惡しかるべき事かは。かやうの事は、物馴れぬ人の有る事なり。
第二百三十五段
主ある家には、すゞろなる人、心のまゝに入り來る事なし。あるじなき所には、道行き人みだりに立ち入り、狐、ふくろふやうの物も、人げにせかれねば、所えがほに入り住み、こだまなど云ふ、けしからぬかたちもあらはるゝものなり。又、鏡には色かたちなき故に、萬の影來りてうつる。鏡に色かたちあらましかば、うつらざらまし。虚空よく物を容る。我等が心に念々のほしきまゝに來りうかぶも、心といふもののなきにやあらん。心にぬしあらましかば、胸のうちに若干のことは入り來らざらまし。
第二百三十六段
丹波に出雲といふ所あり。大社をうつして、めでたく造れり。しだのなにがしとかやしる所なれば、秋の比、聖海上人、其の外も人數多さそひて、「いざ給へ、出雲をがみに。掻餅召させん」とて、具しもていきたるに、各拜みて、ゆゝしく信おこしたり。御前なる獅子狛犬、背きて、後ざまに立ちたりければ、上人いみじく感じて、「あなめでたや、此の獅子の立ち樣、いとめづらし。深き故あらん」と、涙ぐみて、「いかに殿ばら、殊勝の事は御覧じとがめずや。無下なり」といへば、各怪みて、「誠に他に異なりけり。都の苞に語らん」などいふに、上人なほゆかしがりて、おとなしく物知りぬべき顏したる神官を呼びて、「此の御社の獅子の立てられやう、定めて習あることに侍らん。ちと承はらばや」といはれければ、「其の事に候。さがなきわらはべ共の仕りける、奇怪に候ことなり」とて、さしよりて、据ゑ直して去にければ、上人の感涙いたづらになりにけり。
第二百三十七段
柳筥にすうるものは、縱樣横樣、物によるべきにや。「巻物などは、たてざまにおきて、木のあはひより紙ひねりを通して、ゆひつく。硯も縱樣に置きたる、筆轉ばず、よし」と、三條右大臣殿仰せられき。勘解由小路の家の能書の人々は、かりにも縱樣におかるゝ事なし。必ず横樣に据ゑられ侍りき。
第二百三十八段
御隨身近友が自讃とて、七箇條書きとゞめたる事あり。皆馬藝、させることなき事どもなり。其のためしを思ひて、自讃の事七つあり。
一、人あまたつれて花見ありきしに、最勝光院の邊にて、をのこの馬を走らしむるを見て、「今一度馬を馳するものならば、馬倒れて、落つべし。しばし見給へ」とて、立ちどまりたるに、又馬を馳す。とゞむる所にて、馬をひき倒して、乘る人泥土の中に轉び入る。其の詞の誤らざる事を、人皆感ず。
一、當代未だ坊におはしましし比、萬里小路殿御所なりしに、堀川大納言殿伺候し給ひし御曹子へ、用ありて參りたりしに、論語の四、五、六の巻をくりひろげ給ひて、「たゞ今御所にて、紫の朱うばふことを惡むと云ふ文を御覧ぜられたき事ありて、御本を御覧ずれども、御覧じ出されぬなり。なほよくひき見よと仰せ事にて、求むるなり」と仰せらるゝに、「九の巻のそこ/\の程に侍る」と申したりしかば、「あな嬉し」とて、もて參らせ給ひき。かほどの事は、兒共も常の事なれど、昔の人はいさゝかの事をも、いみじく自讃したるなり。後鳥羽院の御歌に、「袖と袂と、一首のうちに惡しかりなんや」と、定家卿に尋ね仰せられたるに、「秋の野の草の袂か花薄穗に出でてまねく袖と見ゆらんと侍れば、何事かさふらふべき」と申されたる事も、「時に當りて本歌を覺悟す。道の冥加なり、高運なり」など、こと/\しくしるしおかれ侍るなり。九條相國伊通公の款状にも、異なる事なき題目をも書きのせて、自讃せられたり。
一、常在光院のつき鐘の銘は、在兼卿の草なり。行房朝臣清書して、いがたにうつさんとせしに、奉行の入道、彼の草を取り出でて見せ侍りしに、「花の外に夕を送れば聲百里に聞ゆ」と云ふ句あり。「陽唐の韻と見ゆるに、百里誤か」と申したりしを、「よくぞ見せ奉りける。おのれが高名なり」とて、筆者の許へいひやりたるに、「誤り侍りけり。數行となほさるべし」と、返事侍りき。數行も如何なるべきにか。若し數歩の心か、覺束なし。数行なを不審。數は四五也。鐘四五歩不幾也。たゞ遠く聞ゆる心也。
一、人數多伴なひて、三塔巡禮の事侍りしに、横川の常行堂の中、龍華院と書ける古き額あり。佐理、行成の間疑ありて、未だ決せずと申し傳へたりと、堂僧事々しく申し侍りしを、「行成ならば裏書あるべし。佐理ならば裏書あるべからず」といひたりしに、裏は塵つもり、蟲の巣にて、いぶせげなるを、よく掃きのごひて、各見侍りしに、行成位署名字、年號、さだかに見え侍りしかば、人皆興に入る。
一、那蘭陀寺にて、道眼聖談義せしに、八災と云ふ事を忘れて、「是やおぼえ給ふ」といひしを、所化みな覺えざりしに、局の内より、「是々にや」と云ひ出したれば、いみじく感じ侍りき。
一、賢助僧正に伴なひて、加持香水を見侍りしに、未だ果てぬほどに、僧正歸りて侍りしに、陳の外まで僧都みえず。法師共を返して、求めさするに、「同じさまなる大衆多くて、え求めあはず」といひて、いと久しくて出でたりしを、「あなわびし。それ、求めておはせよ」といはれしに、かへり入りて、やがて具して出でぬ。
一、二月十五日、月あかき夜、うち更けて千本の寺に詣でて、後より入りて、ひとり顏深くかくして聽聞し侍りしに、優なる女の、姿、にほひ、人より異なるが、わけ入りて膝にゐかゝれば、にほひなども移るばかりなれば、便惡しと思ひて、すりのきたるに、なほゐよりて、同じ樣なれば、たちぬ。其の後、或御所ざまの古き女房の、そゞろごといはれしついでに、「無下に色なき人におはしけりと、見おとし奉ることなん有りし。情なしと恨み奉る人なんある」とのたまひ出したるに、「更にこそ心得侍らね」と申してやみぬ。此の事、後に聞き侍りしは、彼の聽聞の夜、御局の内より人の御覧じ知りて、さぶらふ女房を、つくりたてて出だし給ひて、「便よくは、言葉などかけんものぞ。其の有樣參りて申せ。興あらん」とて、はかり給ひけるとぞ。
第二百三十九段
八月十五日、九月十三日は婁宿なり。此の宿、清明なる故に、月を翫ぶに良夜とす。
第二百四十段
しのぶの浦の蜑の見るめも所せく、くらぶの山も守る人しげからんに、わりなく通はん心の色こそ、淺からずあはれと思ふ節々の、忘れがたき事も多からめ。おやはらから許して、ひたぶるに迎へ据ゑたらん、いとまばゆかりぬべし。世にありわぶる女の、にげなき老法師、あやしの吾妻人なりとも、賑はゝしきにつきて、「さそふ水あらば」など云ふを、仲人、何方も心にくきさまにいひなして、知られず知らぬ人を迎へもて來たらんあいなさよ。何事をか打ちいづる言の葉にせん。年月のつらさをも、「分け來し葉山の」なども相語らはんこそ、盡きせぬ言の葉にてもあらめ。すべて餘所の人の取りまかなひたらん、うたて心づきなき事多かるべし。よき女ならんにつけても、品くだり、見にくゝ、年も長けなん男は、かくあやしき身のために、あたら身を徒らになさんやはと、人も心劣りせられ、わが身は、むかひゐたらんも影はづかしく覺えなん、いとこそあいなからめ。梅の花かうばしき夜の朧月にたゝずみ、みかきがはらの露分け出でん有明の空も、我が身ざまにしのばるべくもなからん人は、たゞ色好まざらんにはしかじ。
第二百四十一段
望月の圓かなる事は、暫くも住せず、やがて缺けぬ。心とゞめぬ人は、一夜の中に、さまでかはるさまも見えぬにやあらん。病の重るも、住する隙なくして、死期既に近し。されども、いまだ病急ならず、死におもむかざる程は、常住平生の念に習ひて、生の中に多くの事を成じて後、閑かに道を修せんと思ふほどに、病をうけて死門に臨む時、所願一事も成ぜず、いふかひなくて、年月の懈怠を悔いて、此の度若したちなほりて命を全くせば、夜を日につぎて、此の事彼の事怠らず成じてんと、願ひを起すらめど、やがて重りぬれば、我にもあらず、取り亂して果てぬ。此のたぐひのみこそあらめ。此の事、まづ人々いそぎ心におくべし。所願を成じて後、暇ありて道にむかはんとせば、所願盡くべからず。如幻の生の中に、何事をか成さん。すべて所願皆妄想なり。所願心にきたらば、妄信迷亂すと知りて、一事をも爲すべからず。直に萬事を放下して道にむかふ時、さはりなく、所作なくて、心身ながくしづかなり。
第二百四十二段
とこしなへに違順につかはるゝ事は、ひとへに苦樂のためなり。樂といふは、好み愛する事なり。是を求むる事止む時なし。樂欲する所、一つには名なり。名に二種あり。行跡と才藝との譽なり。二つには色欲、三つには味なり。萬の願ひ、此の三つにはしかず。是れ顛倒の相よりおこりて、若干のわづらひあり。求めざらんにはしかじ。
第二百四十三段
八つになりし年、父に問ひて云はく、「佛は如何なる物にか候らん」といふ。父が云はく、「佛には人のなりたるなり」と。又問ふ、「人は何として佛にはなり候やらん」と。父又、「佛のをしへによりてなるなり」と答ふ。又問ふ、「教へ候ひける佛をば、なにがをしへ候ひける」と。又答ふ、「それも又、さきの佛のをしへによりてなり給ふなり」と。又問ふ、「其の教へはじめ候ひける第一の佛は、如何なる佛にか候ひける」といふ時、父、「空よりやふりけん、土よりやわきけん」といひて、笑ふ。「問ひつめられてえ答へずなり侍りつ」と、諸人に語りて興じき。
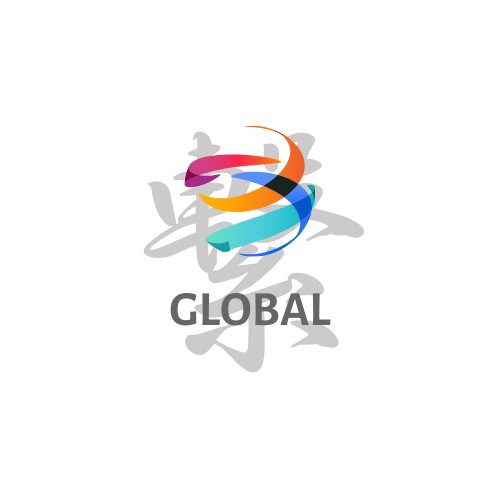

コメント